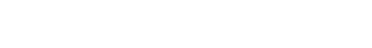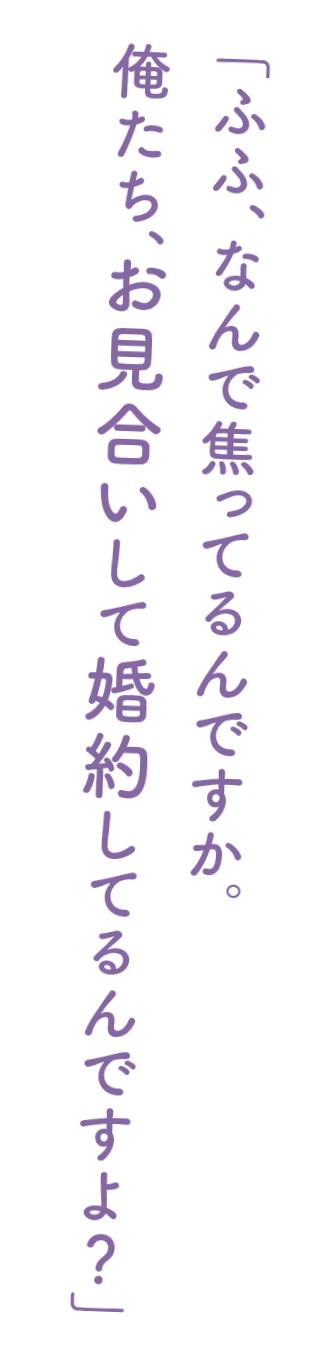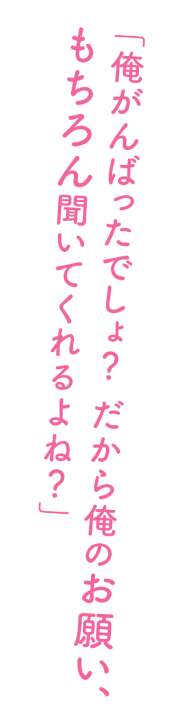- CV.久喜大
- CV.一条ひらめ
- CV.後藤寝床
- CV.冬ノ熊肉
──理想の彼ってどんな人?
かっこ良くて、優しくて、仕事ができて……だけど一番は「愛してくれる」こと。
恋も仕事も「しごでき」な彼がいい!
これは、あなたの乙女心を満たしてくれる彼との、最高に幸せな恋物語。
「しごできダーリン」は、大手化粧品メーカーで働く「しごでき」な彼から甘々に愛されるシチュエーションCD音声です。
「毎日聴きたくなる」をテーマに、愛される安らぎと幸せをお届けします。
♡いちゃラブ・病みなし・ハッピーエンド
♡3回連続ご褒美えっち
♡いっしょに眠れる寝落ちトラック付き
- 2024.5.22「しごできダーリン 絶倫注意!熊系上司のトロあま調教」冬ノ熊肉さんのインタビューを公開
- 2024.5.17プレリュードSS「甘い縁結び」を公開
- 2024.5.17「しごできダーリン After story」サンプルボイス④を公開
- 2024.5.10「しごできダーリン After story」サンプルボイス③を公開
- 2024.5.2「しごできダーリン After story」サンプルボイス②を公開
- 2024.4.26「しごできダーリン After story」サンプルボイス①を公開
- 2024.4.19「しごできダーリン 絶倫注意!熊系上司のトロあま調教」サンプルボイス②を公開
- 2024.4.12「しごできダーリン 絶倫注意!熊系上司のトロあま調教」サンプルボイス①を公開
- 2024.4.2「しごできダーリン 絶倫注意!熊系上司のトロ甘調教」サイト公開
- 2024.2.16「しごできダーリン 犬系後輩は待てが出来ない!」ひつじぐも限定盤特典サンプルボイスを公開
- 2024.2.9「しごできダーリン ダウナー同期は舐め猫エロ猫デキる猫」ひつじぐも限定盤特典サンプルボイスを公開
- 2024.2.2「しごできダーリン 兎系弁護士は年中発情中!」ひつじぐも限定盤特典サンプルボイスを公開
- 2024.1.24「しごできダーリン 犬系後輩は待てが出来ない!」後藤寝床さんのインタビューを公開
- 2024.1.18プレリュードSS「恋が生まれるとき」を公開
- 2024.1.11「しごできダーリン 犬系後輩は待てが出来ない!」サンプルボイスを公開
- 2024.1.11「しごできダーリン 犬系後輩は待てが出来ない!」サイト公開
- 2023.12.20「しごできダーリン ダウナー同期は舐め猫エロ猫デキる猫」一条ひらめさんのインタビューを公開
- 2023.12.20「しごできダーリン 兎系弁護士は年中発情中!」久喜大さんのインタビューを公開
- 2023.12.15プレリュードSS「匂いが俺を惑わせるから」を公開
- 2023.12.15プレリュードSS「完璧な人生プラン」を公開
- 2023.12.14「しごできダーリン ダウナー同期は舐め猫エロ猫デキる猫」サンプルボイスを公開
- 2023.12.8「しごできダーリン 兎系弁護士は年中発情中!」サンプルボイスを公開
- 2023.12.8「しごできダーリン」公式サイト公開
製品情報Products
キャラクター紹介Character
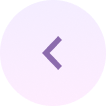
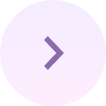
購入はこちらからPurchase
スペシャルSpecial
キャストインタビュー
――収録ありがとうございます。お疲れさまでした!
――今回の企画についての印象や感想を教えていただけますでしょうか。
新しい久喜大をお見せできる良い機会だぜ~、グウェッヘヘヘ~と黒い高笑いがでてしまうくらい胸がドキドキ高鳴る思いでした。
――演じられたキャラクターの魅力をお伺いできますでしょうか。
黒井氏はメリハリと心の距離感を明確にお持ちの方なのだと思います。
教育とは何か、を考えさせられます。
その支えとなっているヒロインはもっと魅力的だと小生は思います。
――黒井唯兎を演じるにあたって心がけた点や難しかった点、または演じやすかった側面などありますでしょうか?
常に六法全書を持ち歩こうと心掛け、結果マッチョになってしまうくらいです。
ヒロインが可愛すぎて「異議ありっ!」と発してしまいそうになるのを堪えるのが難しかったです。
私は兎の中でも「アナウサギ」を好むので演じやすかったです。
――今回の収録で印象に残ったシーンや台詞はありましたでしょうか? また、聞きどころをぜひご紹介してください!
印象に残ったのはこたつをあんな風に使うのだと驚いたことと、「可愛い」をこんなにも発したのは人生で88回くらいしかないので印象的でした。
聞きどころは「寝息」です。一発本番だったので集中するのに収録時間の4割を使用してしまう程の集中が必要でした。
――唯兎は「兎っぽい」部分がありますが、ご自身に「動物っぽいな」と感じる部分はありますか?
まさに「兎」です。寂しん坊なところがあり、黒井さんとも共通するところが多くてビックリです。
次に動物をやるなら兎をやりたい!と思っていたので、オファーを頂いたときは嬉しくてピョンピョンと跳ねたぴょん。
――唯兎とヒロインの二人へ向けて、何か言葉をかけていただけますでしょうか!
兎に角、幸せなら突き進めーーーーーーーーーー!
――最後に、CDの発売を楽しみにしているファンへのメッセージをお願いします!
また貴方のお耳に届く機会を頂きました、久喜大です。いつもいつも皆様のコメントをX(旧Twitter)で拝見しております。
そして、発売後のレビューコメントも更新される度に覗き見しております。皆様の暖かいコメント、喜んで下さる皆様の言葉たちに勇気を頂いております。
8月8日の誕生日を覚えていて下さってありがとう。もう何年も経てば還暦を迎えますが、まだまだ久喜大、皆様が求めて下さる限り頑張り続けたいと思います。その感謝の気持ちを黒井唯兎の心を借りてお伝えできるよう挑みました。貴方の心の奥底まで届きますように。貴方の栄養剤になりたい、久喜大でしたぴょん。
――収録ありがとうございます。お疲れさまでした!
――今回の企画についての印象や感想を教えていただけますでしょうか。
幼少期の頃から「しごでき」な男性に憧れていて、いずれ大人になったら僕もそうなっていくんだろうな…なんて思っていたら全然そんなことはなく、うっかりの連続トホホヒューマンになってしまったので、こうして「しごでき」なキャラクターをやらせてもらえて嬉しいです!
――演じられたキャラクターの魅力をお伺いできますでしょうか。
「しごでき」ではあるけれど、あなたがいないと危なっかしいところが魅力だと思いました。毎日好きなものだけを食べて、体調悪くしてもその理由に気付かずにずっと好きなものを食べてそう…笑 そんなちょっと危うくて狭い彼の世界の中で、あなたのことが圧倒的に一番好き!なところが可愛いな〜って思います。
――音琴環を演じるにあたって心がけた点や難しかった点、または演じやすかった側面などありますでしょうか?
「マイペースでふわっとしていて、あなたが大好き!」というところを主張しすぎると甘ったれふにゃ小僧になってしまって「しごでき」感が薄れてしまうので、ちゃんとかっこいい環の芯は残した上でいちゃつくよう心がけました。
環と同じく僕も飲み会が苦手なので、その点はとても演じやすかったです笑
――今回の収録で印象に残ったシーンや台詞はありましたでしょうか? また、聞きどころをぜひご紹介してください!
飲み会から帰宅したあなたを、自分の匂いをつけるかのようにたくさん舐め回す環…というシーンがあるのですが、嫉妬したりえっちなスイッチが入ったら止まらなかったりな環が可愛いシーンでした。
――環は「猫っぽい」部分がありますが、ご自身に「動物っぽいな」と感じる部分はありますか?
ひらめって名前ですけど、洗濯物を取り込んだらその辺に放りっぱなしで床にダムをつくる時があるので、ビーバーっぽいかもしれないです(雑なビーバー解釈)あとは記憶力が全然ないから鳥かな…いいところなしか…?あ、散歩や走り回ることが好きなので犬っぽいところがあります!
――環とヒロインの二人へ向けて、何か言葉をかけていただけますでしょうか!
2人で美味しいご飯(時に栄養に気を遣った食事)を食べて、いつまでも仲良しでありますように!
――最後に、CDの発売を楽しみにしているファンへのメッセージをお願いします!
マイペースでダウナー、とはいえあなたを想う気持ちはピシっと一直線にかっこいい環をお楽しみくださいませ!
――収録ありがとうございます。お疲れさまでした!
――今回の企画についての印象や感想を教えていただけますでしょうか。
初め企画資料をいただいたときは、別のキャラクターを演じるものと思っていたので「犬か!」と思いました。後藤寝床の声質的に、犬ではない雰囲気のキャラクターを演じることが多いので、逆に犬をやれて楽しかったです。後藤寝床は戌年生まれなので、楽しませていただきました。
――演じられたキャラクターの魅力をお伺いできますでしょうか。
健介の魅力って、絶対的に仕事が出来るのもあり、あまり言葉では出てきていませんがすごく自信を持っている部分ですよね。たぶんヒロインが自分の先輩じゃなかったら容易に落としているだろうなというくらい、恋愛で不自由をしてきていないような自信家だと思っています。だからこそ、立場上落とせない、相手も簡単になびいてはくれないという部分で「セフレでもいいから」と、自分の中であまり取ってこなかったシチュエーションを用意してまでヒロインと繋がっていたかったんだなあと考えると、そこが愛らしく犬っぽいところなのかなと思いましたね。
――柴田健介を演じるにあたって心がけた点や難しかった点、または演じやすかった側面などありますでしょうか?
犬系ということで、初めは必要以上にハアハアするのかなって思ったんですよ。でも家で練習した時に、ハアハアしすぎるとさすがに気持ち悪いなと思いまして。ハアハアは抑えめにしようと思いつつも、初めにいただいた資料に「舐め犬」と書かれていたので、その部分は守ろうと考えていました。ただ、ベロベロベロベロし過ぎると変態に見えてしまって、ただでさえこの子はキスと耳舐めが過剰に多いので、塩梅を意識しました。健介は「舐めたい」奉仕型ではあると思うんですが、先輩という相性のいい人に会えたからよかったねと思いますね。
難しかった点としては、季節柄、どうしてもハアハア芝居で喉が乾燥に負けて音がざらつき、ハスキーになってしまったところです。頑張ってシェパード声を出そうとするんですけど、すぐにシベリアンハスキーみたいになってしまうので、そこを少し気を付けました。
――犬繋がりで、『獣人水泳部!』を少し思い出しますね。また犬をお願いしてしまいました…!
そうなんですよね。あっちは水泳ということもあって透明感があったなと思います。独逸クンは面白いキャラでしたね。獣人なので当然ではあるのですが、健介よりもあの子のほうが犬ですよね。
――今回の収録で印象に残ったシーンや台詞はありましたでしょうか? また、聞きどころをぜひご紹介してください!
彼の「頼られたい男・柴田健介」みたいなキャッチフレーズですかね。なかなか恥ずかしくて言えないフレーズだと思うんですけど、たぶん本人にとっては恥ずかしいことではなくて、「もしかしたらこの先輩は自分が犬だと擦りこめば振り向いてくれるかも!」というような、たまたま出ちゃったのではなく、わざとキラーワードとして使う頭の良さがあると思ったので、そこが好きですね。わざと言ったように見せて、より「仕事ができる男なのかもしれない」とヒロインに思わせていると想像していました。ちなみに資料では「健介はHシーンではSになる」と書いてあり、それを受けて「健介は彼女を手玉にとれていないので、Sになりたい気持ちはあるけど彼女の手玉に取られるよね」という感じで芝居をしてしまい、ファーストテイクではちょっと喘ぎすぎました(笑)
――健介は「犬っぽい」部分がありますが、ご自身に「動物っぽいな」と感じる部分はありますか?
やはり戌年生まれというのもあってか、生まれた時の赤ん坊の写真ではマズルが少し出ていて、本当に犬っぽかったんですよ。それを見ていたおばあちゃんが「犬みたいに可愛かったのよ」と喜んでいました。だから犬はずっと小さいころから親和性があるなと思っていましたね。
――日頃の癒しになっているものがありましたら教えてください!
後藤寝床的には、他の方が出演しているシチュエーションCDを聴くことでしょうか。他の方の演技を聴いて、その方にネット上で雑絡みしに行っています。「パイセン聴きましたよ!」と言うと「そうやって絡んでくるやついないよ」なんて返されます(笑) 僕は2年休んで1年働くスタイルのルーティンを組んでいるのですが、この作品が復帰1発目なので、2年間のうちに色んな人の演技を聴いて、吸収したことを生かそうと思っていました。そういう意味では、今回オーダーにあった息の芝居は、色んな吐息のバージョンを試した作品になったと思います。癒しは「他人の喘ぎを聴く」ですね。
――健介とヒロインの二人へ向けて、何か言葉をかけていただけますでしょうか!
もう本当にこれだけですね。「共依存にならないように気を付けて」。健全な生活を。何よりまずは「太陽を浴びる」ですね。一緒に朝散歩する生活を心がけてくださいとお伝えしたいです。
――最後に、CDの発売を楽しみにしているファンへのメッセージをお願いします!
後藤寝床、2年間の充電期間を経て、ただいまこの業界に戻ってまいりました。また1年、馬車馬のように働かせていただきますけれども、この2年間で見聞きしたことや先輩方のお芝居を存分に生かして、新たなものとして再構築した後藤寝床の声のチャレンジになります。ぜひ真っ暗な部屋で目をつぶって、ヘッドホンをしながら吐息を感じつつ聴いていただきたいなと思います。
――収録ありがとうございます。お疲れさまでした!
――今回の企画についての印象や感想を教えていただけますでしょうか。
ありがたいことに色々とひつじぐもさんにはお世話になっておりますけれども、その中でも特に二人の甘いシーンを中心にしていたなという印象でした。
――演じられたキャラクターの魅力をお伺いできますでしょうか。
真弘さんが仕事が出来る・頼れる上司というところもあるんでしょうか、よりヒロイン目線での「普段仕事が出来てみんなから頼られている真弘さんが自分にだけ見せてくれる面」と言いますか、意地悪さも全て愛情から来ていると言いますか、とにかくヒロインのことが好きで、甘やかして、自分が愛した大切にしたい人に対して、持ち前の包容力をもって甘えに甘やかすというのが、今回の目線での彼の魅力なんじゃないかなと思いますね。
――大熊真弘を演じるにあたって心がけた点や難しかった点、または演じやすかった側面などありますでしょうか?
冒頭の本当に最初の方は仕事をしているオフィスでの真弘さんのシーンがあったので、同じ人物としてちゃんと繋がりながらも、しっかりと仕事モードとヒロインと1対1になったときのものが上手いことグラデーションになって段々深く濃くなっていければなと思いながら演じました。今回コンセプト的にもあるんでしょうけど、とにかく甘やかす・慈しむ・可愛がるというのが強く台本を読んでいて感じたので、一辺倒にテンポや感情のカラーが単純にならないように、聞いていて「はい変えました」みたいなわざとらしさが出ないように出来ていたらいいなと思います。演じやすかった側面は、彼の心根として「とにかく相手のことが大好きだ」というのは演じやすい面ではありながらも、先ほど話したような一辺倒にならないようなバランスの調整は難しい面もあり、表裏一体という感じですね。
――今回の収録で印象に残ったシーンや台詞はありましたでしょうか? また、聞きどころをぜひご紹介してください!
今回はお付き合いしているところから始まっているので、二人の気持ちが通じ合っていて、日常生活をすごく楽しんでいるところの中を描いているわけですから、そういった意味では、自分たちの生活や関係を一歩前に進めるシーンは印象的です。そのシーンは真弘の男らしさ・自分についてきてほしいみたいな意識は持ちながらもあくまで相手の気持ちを尊重していて、「もし断られたとしても」みたいなことを言うんですけど、自分はこうしたいというのは強く持ちながらも相手の気持ちはないがしろにしないっていう、男らしさと思いやりのバランスみたいなところは意識しながら演じていました。なので、あの付近のシーンは意識しましたし、その後思いが通じ合ってからが、彼自身が自制心みたいなものを意図的にちょっと脇に置くところでもあるので、その流れは印象に残りましたし、かつ聴きどころじゃないかなと思っております。
――真弘は熊をモチーフにしているのですが、ご自身に「熊っぽいな」と感じる部分はありますか?
名前ですね。正直自分自身に熊っぽい部分はあまり無いかなと思うので、私の名前です。
――作品タイトルの『しごでき(仕事ができる)』にちなみ、「仕事ができるな」と思う人物像や、理想はありますか?
「仕事が出来る」というのも色々種類があると思っていて、今回は真弘さんがどちらかと言えばチームをまとめる上司というのもあるので、その観点で僕がついていきたいと思う人の話になっていまいますが……。人や部下の話に耳を傾けられて、すごく広い視野で気遣いが出来る、かつ自分自身で譲れないラインはしっかり持っていてきっぱりと意思を通すべきところは通せる、という、数値化じゃないメンタル的な仕事が出来る人が、ついていきたい上司になりますかね。
――真弘とヒロインの二人へ向けて、何か言葉をかけていただけますでしょうか!
末永く仲良くイチャイチャしていてください、ですね。
――最後に、CDの発売を楽しみにしているファンへのメッセージをお願いします!
今回、大熊真弘の声を担当させていただきました冬ノ熊肉でございます。体は大きく、気は優しくて力持ちじゃないですけど、しごできダーリンのこれまでの3作とは違った人物像だと思います。今回のCDというのはヒロインにだけ見せる面っていうのがよりフィーチャーされているCDだと思いますので、冒頭、真弘さんが仕事をしているシーンから真弘さんの普段の仕事姿を想像していただきながら、自分だけに見せる顔・自分だけに聞かせる声・他の人に対して絶対に使わない声音が今回の特徴だと思うので、仕事中とのギャップの想像も膨らませて楽しんでいただけたら幸いでございます。
本編が始まる前の、彼との出会いの物語
プレリュードSS
「では、お先に失礼します。お疲れさまです」
身支度を整え、出社したときと寸分違わぬ格好で、事務所を後にする。黒井唯兎は、いつも通りの時間に退社した。
企業弁護士の仕事は、イレギュラーな急ぎの案件もそれなりにある。それらを上手くさばいてこなし、定時に帰ることは、唯兎にとって自分ルールのような目標になっていた。その達成に向けて、内心どこか楽しんで仕事をこなす日々を送っていた。
一人暮らしのマンションに、普段通りの時間に帰宅したところで、私用のスマートフォンが鳴る。実家に住む母親からの着信だった。
「──お見合い?」
実家の母親からの縁談話。直々の連絡なだけあり、お相手の家柄は申し分ないという。
「わかった。来週、一度顔を出すよ」
唯兎はこの話を了承した。自分なりに考えていた人生プランに基づいて、そろそろ良い人を見つけてもいい頃合いだと考えていたからだ。
しかし職業柄、不特定多数の女性と知り合う機会などそうそう持てるはずもなく、交友関係でも浮いた話はなく、今の状況に行き詰まりを感じていた。
突然の降って湧いたような縁談話。ダメなら次に行き、うまく行くようならスムーズに事が運べばいい。唯兎はどこか気軽に、そう思っていた。
そうして話はまとまり、迎えた顔合わせの当日。対面に現れた女性の、緊張で少しぎこちないが、人の良さそうな笑顔を見て、唯兎は一目でその人を気に入っていた。
魅力的な笑顔を前にして、唯兎もできるだけ明るく笑顔でいようと努めていた。両家ともに、親同士の空気も悪くない。
二人で話す機会を、と両家の親たちが気を遣い、席を離れる。彼女との一対一の会話も、変に淀むことなく進み、二人はいつのまにか談笑していた。唯兎の目には目の前の女性が、十分すぎるほど魅力的に映っていた。
「あの、……実際のところ、あなたはどのくらいこの結婚に、乗り気なんでしょうか」
そう尋ねる唯兎を見て、彼女は少し驚く。きっと自分のことを、もっと冷たい人間だと思っていたのだろう、と唯兎は思っていた。お見合い写真では、あまりいい笑顔を作れなかったから。
「私は……あなたの事が、その……とても、気になっています。よかったら、今後も付き合ってくれませんか。少しずつでいいので」
唯兎の申し出に、彼女が了承する。幸せに思いながらも、これで婚約という事になるのだろうか、とどこか現実味が感じられないでいた。
入籍や結婚は、後々でも構わないと考えていた。唯兎の考えていた人生プランにまだ時間はある。まずはこの女性と出会えた喜びを、唯兎は静かに噛み締めていた。
次に会う約束をして、唯兎が彼女と二人で行ったのは、料理に定評のあるホテルのレストランだった。唯兎のお気に入りの店、お気に入りのメニュー。それを彼女が喜んでくれているのがわかって、唯兎は好みを分かち合えたことを嬉しく感じていた。
二人はそれから何度も、週末に一緒に出かけて、楽しい時間を共有した。彼女の好きなものを知って、自分の好きなものを教えて。
週末に会う機会が次第に増えていき、デートの終わりにはいつも、唯兎は彼女を最寄りの駅まで見送っていた。
唯兎が焦って彼女に手を出さなかったのは、清いお付き合いだと両親にアピールするためだったが、いつの間にか唯兎自身が、彼女との仲が少しずつ進展していくのを楽しんでいた。
そうして季節は初夏。金曜日、いつも通り唯兎は定時で退勤した。明日は彼女と約束していたデートの日だ。
待ち合わせ場所と時間を伝えようと、アプリを立ち上げ、彼女とのチャット欄にメッセージを送信していく。
『明日はココで、11時頃合流しましょう』『できればお腹は空かせておいて下さいね。ランチも良いお店を見つけておきましたから』──
「……?」
唯兎の送ったメッセージに対して、すぐ既読はついたものの、その後に彼女から中々返事が来ない。いつもならすぐに、楽しみです、なんて返事が返ってくるのに。
じっと待っているうちに、送られてきた返事は『わかりました』の一言だけだった。
彼女の対応に何かひっかかるものを感じ、唯兎はすぐさま電話をかける。
「もしもし。あぁ……出てくれて、ありがとうございます」
すぐに彼女と電話が繋がり、唯兎は少し安心する。同時に、その声色を聞いた事で、違和感がはっきりと浮かび上がる。
「もしかして、何かあったんですか? ……あったんですよね? 今から向かいますから。駅前まで出てこられるようなら、お会いして話しましょう。それでは──」
半ば無理やり会う約束を取り付けて、唯兎はすぐに駅へ向かった。電車へ乗って数駅、いつも別れる駅前まで出てきた彼女は、いつも週末に会うときと比べて、明らかに疲れた顔をしているのが見て取れた。
「教えてください。君に何があったのか……君が心配で、飛んできたんです」
それから二人は近くのカフェに移動して、一息ついてから、彼女の話を聞いた。
彼女の働いていた会社が突然倒産して、すぐにでも会社の寮を出ていかなければならないこと。その事を両親に伝えられていないこと。この一週間、どうにかできないかとあちこちを奔走していたこと……。
唯兎は最初、彼女がすぐに自分を頼ってくれなかったことが、ショックだった。あなたの未来の夫になるはずの相手なのに、と。
しかし彼女の話を聞いているうちに、他の誰かに迷惑をかけないよう、彼女なりに気を遣いながら、状況を善くする方法を模索していたと解り、唯兎は安心した。
彼女にとって、婚約者である唯兎を頼るのは……他に何も解決策が見つからなかったときの、最後の手段だった。
(この人は、なんて……いじらしく、気高いんだろう)
「……話は解りました。そしてこの状況を打破する手も、ひとつ見つけました」
今の俺にできることは、彼女の中の優先順位を変えてあげることだけ。唯兎は決心して、彼女にある提案をした。
「俺の部屋に来ませんか。いずれ結婚して一緒に暮らす予定でしたし、俺は構いません。現実的に考えても、次のことを焦って決めて、下手に失敗するくらいなら、未来のことを落ち着いて考える時間が、あった方がいい。そうでしょう?」
本来想定していた順番が入れ替わってしまうことに、唯兎も内心で抵抗はあった。だけどそれ以上に、目の前の大事な人が困っているときに、何もできない男ではいられないと強く思っていた。
唯兎の提案に、はじめは迷っていた様子の彼女だったが、他に手はないと心を決め、唯兎の提案を承諾した。
「そうと決まれば、明日のデートプランはキャンセルですね。この週末の間に、引っ越しの準備を進めましょう」
細かな段取りを決めて、業者の手配をする間、唯兎は自分の人生プランが、彼女の色で塗り換わっていくのを感じていた。
目を伏せ、気持ちを鎮める。視界の情報がなくなった分、他の感覚器──嗅覚を鋭敏な状態にする。
眼前にあるのは、調合したばかりの香料。単なる匂いとしてではなく、香りそのものの存在を全身で感じ、向き合う──調香研究部門・音琴環の集中力は、無遠慮なノックの音で不意に途切れさせられた。
「…………」
環が返事をしないでいると、レバーが勝手に回って、営業職の女性社員が研究室へと入ってきた。やっぱりいた、なんて言いながら彼女が環の机に置いたのは、書類の詰まった一冊のファイル。表紙には『お客様からのご要望』と書いてある。
「……なに? また来たの」
彼女の次に言う言葉は大体予想できていたが、環はあえて冷たく返した。環の返答の温度を意に介さずに、彼女は予想通りの言葉を言う──資料を参考に新しい香料を開発しよう、と。
「……あのさあ、俺はそういうやり方じゃないって、何回言ったらわかるわけ?」
そこからは、いつもの言い争いが始まった。環はどちらかと言えば、自分の感性を頼りに研究を進めたいタイプだった。彼女のやり方はその逆で、問題を解決したい顧客に向けて作っていくことで確度の高い商品を生み出そうというスタンス。
どちらも喧嘩腰のまま、両者とも一歩も譲らずに議論は平行線を辿っていく。
「だいたい、そんな数の資料を渡されたって困る。匂い一つで、全部の問題が解決するわけないんだから、何が課題なのかを見つけてからでしょ」
最終的に彼女が納得した顔で「もう一度しっかりヒアリングしてくる」と言い残して、研究室を出ていく。後には徒労に巻き込まれた環だけが残されて、ひとりため息をついていた。
「……ハァ、全く」
環は自分の椅子に深く腰掛ける。目の前の机には、彼女の持ってきた書類ファイルが開かれたまま残されている。
同期である営業の彼女と環は、顔を合わせればいつもこんな風に言い争いになってしまっていた。
もともと環は、大勢の人と過ごすよりも自分一人でいる方が好きなタイプだ。人と関わるのは苦手で、大声で意見をぶつけ合うなんてことは、本来避けるべき出来事だった。
静かに調香の研究をしていたいからこそ、この会社の研究職に就いたのに。
それに環だって、彼女の言い分に一理あることを、内心では認めている。感性だけでは製品開発はできないことだって、わかっている。なのに。
(……それなのに──)
彼女を前にすると、どうしても素直になれない自分がいる。いじわるしたくなる。さっきの言い争い自体も、内心で避ける気のない自分がいることに気づいていた。
環はその原因に心当たりがある──彼女の匂いが、妙に気になるからだ。
彼女の持つ、固有の香り。言い争いとは無関係なところで、環はその匂いを気に入っていた。
(あの匂いはウチの製品にはない……かといって、競合他社のフレグランスでもない)
いっそ成分分析にかける機会はないかと思うほど、その香りは環の心を掴んでいた。
言い争いで喉がすっかり乾いた環は、飲み物を求めて研究室を出た。ついでに、先程彼女が置いていったファイルを返すために。
同じ階、営業部のフロアへと向かう途中で、環は彼女を目撃した。
「あれって……」
営業の彼女が、先輩社員を捕まえては、何事かを聞きただし、手前のメモ帳に書き留めているのが見えた。不器用で、とても効率的とは言えないが、その姿からは──
「……ふん」
話し合いが一段落し、先輩社員が過ぎ去った後も、メモ帳に何か書き留めている彼女に近づき、環は内心で意を決して話しかけた。
「ねえ、来て。……休憩するから」
半ば無理矢理彼女を連れ出し、自販機の立ち並ぶ会社の休憩スペースまで連れてきた。ベンチに座らせて、環は違う種類の缶コーヒーをひとつずつ買って、彼女の前にふたつ並べた。
「ん。好きなほう、選んで」
片方を手に取った、彼女の隣に座る。ありがとう、と小さく呟くのが環には聞こえた。
「お前、やる気あるのは、わかるけど……なんでそんな、頑張ってるの」
彼女はコーヒーに口をつけてから、自分がやりたくて始めた仕事だから、と答えた。
「やりたいことだから……ふーん」
胸の内のモヤモヤをうまく伝えられない環の隣で、彼女が缶コーヒーを飲み切る。それから、ちゃんと話し合うために二人で飲みに行こう、と彼女が提案した。
「え、今日? ……うん、いいよ。その代わり、店とか予約、全部任せるね」
環はその提案を、自分でも内心驚くほど素直に受け入れた。人と一緒に食事に行くのを、面白そうだと思ったのは、環にとって初めてのことだった。
その心変わりは──隣に座る彼女の匂いだけでは、なかったのかもしれない。
「……はい、かんぱーい」
彼女が選んだのは、会社からほど離れたネパール料理屋だった。シンハービールの注がれたグラスを打ち鳴らし、喉を鳴らしているうちに、見るからにスパイスの効いた料理がいくつも運ばれ、テーブルの上に並ぶ。
「ふーん……面白いじゃん」
静かな店内と、普段嗅ぐことのないエスニックな香り。いい意味で予想を裏切られた環は、彼女の選択を面白く思っていた。
「それで、何。言いたいことあるんじゃなかったの」
料理を楽しみながら、環はそう切り出した。彼女は改めて、一対一となった環に向かって、自身の想いを口にする。
張り切って配属された部署で、まだ自分の納得する結果を出せていないこと。次の新商品のプロジェクトを、頑張って成し遂げたいと思っていること──
「ふーん……新商品って、作るのは俺なんだけど」
いたずらっぽく笑う環に、だからあなたと話さなきゃいけないと思ったの、と彼女は返す。
「そっか。……まあ、いいんじゃない。お前が頑張ってるのはわかるし、俺だって失敗するつもり、ないし──」
手にしたビールを飲みきってから、環は言葉を続ける
「お前の言いたいことや聞きたいこと、これからも全部言いに来なよ。……とりあえず、聞くだけは聞くから」
お酒を飲んでいても、これだけスパイスの匂いに囲まれていても、絶対にそれと分かる彼女の香りを前にして──環は、彼女に対する気持ちが特別なものであることを、認めていた。同時に環の心の内で、次のプロジェクトを絶対成功させるという決意が芽生える。
──彼女の笑顔のために、自分にできることを精一杯やろう。まだ言葉にできないこの恋心を、いつか伝えられるその時までは。
「柴田ー。資料できたか?」
「もうちょいです。あと五分でいけます」
「OK.それ出来たらすぐ行くぞ」
「はい!」
化粧品メーカー、ANMNホールディングスに健介が入社してから二年が過ぎた。営業に配属され、夢中で仕事に明け暮れていたら二年なんてあっという間だ。
健介は、作成中の資料の数字を確認して「よし」と声を上げた。
完成だ。すぐに、声を掛けてくれた上司と合流して、顧客の元へ向かう。
仕事は面白かった。学生時代は、全てにおいて「なんとなく」「楽しいから」というスタンスで適当に生きてきた健介だったが、仕事を始めてから変わった。入社当初は、学生気分が抜けず易きに流れることも多かったが、営業という仕事が性に合っていたのだろう。毎日忙しくする充足感や、仕事が取れたときの達成感で、次第にハマっていった。元々人とのコミュニケーションが好きだったことも功を奏したのだろう、仲間と成し遂げることや顧客との信頼関係が培われていくことに大きな喜びとやりがいを感じていた。
(そういえば、全然遊ばなくなったよなあ)
仕事に忙殺されて、というわけではない。ただ単に、遊びよりも仕事のほうが面白くなった。健介にとってはそれだけだった。
そんなある日のこと、大手の新規獲得に向けて新チームが結成されることになった。
そのメンバーに入ることができただけでも健介は嬉しかったのだが、もうひとつ、嬉しいことが起きたのだ。それは、憧れの人と同じチームになれたこと――。
「先輩、これからよろしくお願いします!」
元気よく挨拶をしすぎたのか、一年上の先輩は少し驚いた顔をした。けれどすぐににっこり笑って、よろしく、と返してくれる。その反応が嬉しくて、健介はなおも前のめりになった。
「ほんっと、マジ嬉しいです。先輩と一緒に仕事できるとか……、初めて会ったときから一緒にやりたかったんです! 先輩は、俺の憧れの人なんですよ!」
大げさだと彼女は笑っているが、本当のことなのだから仕方がない。
あれは、健介が入社してまだ四か月ほどのことだった。慣れない仕事に無我夢中で、空回りも多かったあの時、彼女の姿に刺激を受けた。
自分とたった一年しか入社の違わない彼女が、生き生きとかっこ良く仕事をしている。それだけでも健介の目に留まるには充分だったが、最も大きなきっかけはあの日。彼女が自分の力で大きな契約を取ってきたという、あの日だった。
オフィスに駆け込むようにして戻ってきた彼女は、開口一番「取れました!」と叫んだ。ちょうど珈琲を買って戻ってきた健介は、その一部始終を見ていた。満面の笑みで目を輝かせて、大きな声で上司に報告をしている。
その瞬間に、ワッと彼女の周りに人が集まったし、皆で喜んでいた。その光景は彼女の仕事の実力と、そして社内の人望を表すには充分だったし、新入社員の健介には眩しすぎた。
一年後、自分はあんなふうになれているだろうか?
俺も、あの笑顔のそばに立ってみたい。
様々な思いが入り交じり、健介は突っ立ったままその様子を眺めてしまった。あのときの笑顔が忘れられない。仲間に囲まれて胸いっぱいな様子の彼女の姿が忘れられない。
あんなふうになりたい。なれると思う。なってみせる。
仕事が面白くなり始めていた健介へ、更なる刺激とやる気を与えたのは、紛れもない彼女だった。
そんな憧れの先輩と同じチームで働ける。
純粋な憧れ、目標。もちろん最初はそれだけだったのだが……。
(……あれ? 先輩?)
市場調査に明け暮れて、リフレッシュしようとランチに出た先で、健介は彼女を見つけた。会社から少し離れたところにある、イタリアンレストランだ。初めて足を運んだ店で、偶然にも彼女を見つけるなんてラッキーだと思った健介は、迷わず声を掛けてみることにする。
「先輩、偶然ですね!」
そんなに驚かせるつもりはなかったのだが、彼女はビクリと大きく肩を震わせた。ひと呼吸置いてから、笑顔で顔を上げる。
けれどその笑顔がいつもの笑顔ではないことに、健介はすぐに気がついた。目も赤く腫れているし、明らかに元気がない。
「ひとりです? 良かったらとなりいいですか?」
頷いてくれたけれど、健介は果たして本当に良かったのかと座りながら思った。ひとりになりたいから会社から離れた店でランチをとっていたのかもしれない。俺に気を遣ってくれたのかもしれない。
けれど健介は、どうしても彼女のそばにいたかった。
「やー、先輩にこんなとこで会えるなんて運命かも! あっ、先輩は何食べてます? 俺、この店初めてで、たまには足伸ばしてーっていうか、あー、あはは、アレっす。ちょっと煮詰まってたっていうか。ほら、俺今、市場調査めっちゃ頑張ってるじゃないですかー。けっこう大変なんですよ。先輩、そーいうの得意です?」
なんとか笑顔にしたい。その一心だった。
もちろん、いくらポジティブ思考な健介と言えど、今笑ったくらいで彼女の問題が解決するとは思っていない。だが、少しでも彼女の心が軽く明るくなれば、と心から願っての言動だった。
その後も普段通り、いや普段以上に明るく接する健介を前に、彼女はくすくすと笑い始めた。
「……あ、俺、なんかヘンなこと言いました?」
すると彼女は……。最初はうるさくて迷惑だと思っていたがなんだかおかしくなってきたと言う。けっこうハッキリものを言うんだな、と思いながら、健介はすごく彼女らしいと好感を持った。
その上、健介と一緒にランチができて良かったなどと言う。元気が出ないときはここでランチをすると決めているが、健介がいると元気がかけ算で増える……と。
(あー……なんだこれ)
心臓がやたらうるさい。泣き出しそうにも見える顔で笑う彼女が、愛おしくて堪らない。
(マジ……なんだよ、これ)
「……俺も、先輩がいたら、かけ算です」
どういうことかと言いながら、彼女はまたひとしきり笑った。
そうだ。初めて彼女の笑顔を見たときから、その笑顔が好きだった。明るい声や仕事への姿勢、その全部が好きだった。
その好きはきっと最初から……、ただの憧れではなかったのだ。
温めていた想いが一気に沸き立つのを感じながら健介は「この人が欲しい」ハッキリとそう、自覚した。
ただ、この恋が実るのは、まだもう少し先のお話――。
本編へつづく
ANMNホールディングスに入社して13年。今では主任として、一癖も二癖もある営業部の面々を取りまとめるポストにいる大熊真弘には、とある噂があった。それは、「眼力で人を殺す」という、お世辞にも良い噂とは言えないもので――
「君。ちょっと来てくれるか」
声をかけた女性社員が、それでなくとも沈んでいた顔をさらに引きつらせる。周りもその様子を、ハラハラした面持ちで見守っている。真弘には、彼ら彼女らの胸の内が、手に取るようにわかった。
(何も、取って食いやしないんだがな……)
取引先でミスをしてしまったと部下から報告を受けたのが小一時間前。それから真弘は先方に謝罪の連絡を入れ、事態の収拾に駆けずり回った。無事に一件落着となったところで、部下の女性を会議室に呼び出した、というのが今の状況だ。
「ミスは誰にでもある。大事なのはその後だ。次に同じ状況が訪れた時、どう行動するか考えてみよう」
「えっ? あ、はい……」
ひどく叱られるだろうと予想していた部下は、思いがけず優しく声をかけられ、目を丸くする。
「それと、得意先から、君へのメッセージを預かってきた。君にはいつもお世話になっているから、これに懲りずに頑張ってほしい。またよろしくお願いします、とのことだ」
「あ……」
得意先からの労いの言葉を聞いた瞬間、いよいよ彼女は涙を流した。それから二人一緒に会議室を出ると――
「あっ、出てきた!」
「ああ、目が赤いじゃない」
外で待ち構えていた社員たちが、あっという間に部下を取り囲む。明らかに、真弘からこっぴどく叱られたのだろうと誤解しているようだ。
(やれやれ……)
この長身とガタイの良さが、周囲の人間に圧を与えているという自覚はある。顔つきも、お世辞にも優しく穏やかとは言えないだろう。事実、仕事をするうえで会社の人間には厳しく接することも少なくない。だが……。
(まあ、いい。こういうことは慣れっこだ)
真弘は気を取り直し、自身のデスクに座って仕事を再開した。週末には大事な予定が入っている。どうしてもその日までに、仕事を片付けておかねばならなかった。
***
「あれ、君は……」
そうして迎えた週末。真弘が意気揚々と向かったのは、ベルギーから来日するカリスマチョコレートシェフが開催するスイーツビュッフェであった。いつもなら一人でスイーツビュッフェに行くなど考えもしないが、このシェフの来日は稀有な機会。真弘としては、どうあっても見逃せなかった。強面で通る彼は、社内ではその外見から怖がられがちだが、実は甘いものに目がない――その事実は、ほとんどの人間が知らない秘密だった。
その入口でばったり出くわしたのが、部下である彼女だ。どこか幼さの残る顔つきの奥に見え隠れする、凛とした芯の強さ。その表情にやけに惹きつけられた。
聞くところによると、一緒に来るはずだった友人が急遽来れなくなり、どうしようかと迷っていたところだったと言う。
「そうか、それは災難だった――……」
「あっ、ペアのお客さまですね。お席までご案内します!」
「えっ? いや、俺たちはペアじゃ……」
一緒にいたため店のスタッフに間違われ、そのまま席に通されてしまう。
「申し訳ない。こんな形で一緒になるなんて」
けれど彼女は、こちらこそ、と笑う。ご一緒できて、嬉しいです、とも。
「それなら良かった。これも何かの縁だな。せっかくだし、楽しもうか」
こうして二人は、一緒にスイーツビュッフェを楽しむことに。次々に甘いスイーツを選んでは表情を綻ばせる真弘の姿を見て、彼女は思わず見とれてしまった。
「俺が甘いものが好きだって、そんなに意外か?」
真弘が冗談めかして尋ねると、彼女は、ゆっくりと頭を振った。主任が常に周りに気配りをしていること、実は優しいこと、ずっと知っていました。そう言って笑う。だからスイーツ好きでも納得ですし、共通点が見つかって、嬉しいです、と。
「そう、か。ありがとう」
社内で誤解されても、構わないと思っていた。なのに彼女は、自分のことをちゃんと見ていてくれている。言いようのない喜びが、真弘の胸を満たしていった。
***
それから二人の距離は自然と縮まり、いつしか、休日を共に過ごすほどの仲にまで進展していた。他社を調査する。そんな名目で、様々な場所に足を運んだ。そんなある晩、彼女が残業でオフィスに残る中、真弘は彼女のデスクに近づいた。
「まだ残っていたんだな。新商品のプロモーション案を練っているのか」
真弘の声に、彼女は手元の資料を差し出した。真弘がふっと微笑む。
「うん、OKだ。よくできてる。これなら通るだろうな」
ふたりは休憩室に移動し、真弘は彼女にココアを買って渡す。
「――そういえば、今度の週末、問題ないか? 申し訳ないな……俺のために時間を作ってくれて」
真弘が躊躇いがちに尋ねると、彼女は少し顔を赤らめながら、照れくさそうに微笑んだ。『全然大丈夫ですよ。主任と過ごす時間は……楽しいし、いろんなことを教えてもらえるので』
彼女の言葉とその照れくさそうな様子に、真弘の心の奥底で何かが動いた。彼女の笑顔が、これまで以上に輝いて見え、その瞬間、真弘は自分の中に芽生えている感情――恋心――に気づいた。
この笑顔を見ていたい。もっと一緒に過ごしたい。この笑顔を奪われるなら、心が引き裂かれそうだ。その一瞬で思った。だから。
「そうか。助かるよ」
そう言うのがやっとだった。
彼女と過ごす時間が、どれほど真弘の中で特別になっているか。しかし一方で、そのことに対して、彼女は部下なんだぞ、と真弘の理性が囁く。これ以上踏み込むことは許されない。仕事と私情の間の微妙なバランスに、葛藤もまた、大きくなっていくのだった。
***
週末がやってきた。約束していた商品リサーチのため、彼女と二人で街を歩いている。通りを進む中、真弘はショーウインドウの新しいディスプレイに目を留め、それをきっかけに話を始める。
「この前の会議で話していた、新しいマーケティング戦略。これを実際に見ると、理論と実践のギャップを感じるな」
彼女と熱心に意見を交わすうち、ふとした瞬間、ショーウインドウに映る、彼女の小柄さに心が動かされた。いつものことだが、今日はそれがやけに愛らしく感じられた。オフィスで見かけるスーツ姿とは違う、ふわりと揺れるワンピース姿がそうさせたのかもしれない。
「君は可愛いな…………あ」
思わず口をついて出た言葉は、もう取り返しがつかない。真弘は慌て、彼女は顔を真っ赤にしてうつむいた。沈黙の中で、真弘は自己嫌悪に陥った。
(……どうして部下に対してこんなことを……)
そこで、二人の間に流れる微妙な空気を一変させる声が聞こえた。
「すみませーん。今、カップルのストリートスナップ撮らせてもらってて。一枚いいですか?」
「いや、俺たちはカップルじゃ……」
「はい、撮りますねー。笑ってー!」
「あ……」
こんな感じです、と見せられた写真は、二人して表情がぎこちなく、けれど確かにカップルと言われればそう見えないこともない。『私たち、恋人同士に間違えられちゃいましたね』そう照れながら言う彼女の顔はどこか嬉しそうで、真弘はときめくと同時に強い危機感を覚えた。
(もう、彼女には近づかないことにしよう。……このままでは、本当に女性として好きになってしまう)
***
それからしばらくの間、一緒に出かけることも、必要以上に会話することもない日々を過ごした。真弘は意識的に、彼女との接点を避けていたのだ。
時折、彼女の悲しげな表情が気になったことはある。だが、それでいいのだと思っていた。
(俺たちは上司と部下だ。そうであるべきだ。それ以上でもそれ以下でもないのだから)
しかし、あの日はやってきた。――バレンタインデーだ。
「チョコ? 俺に?」
こっそり呼び出された彼女に手渡されたのは、綺麗に包装されたチョコレート。それはあのスイーツビュッフェの日、真弘がとくに好きだと話したブランドの、バレンタイン限定のチョコレートだった。
(あの日の話を、覚えていてくれたんだな)
その事実は、心のバリアを崩すのに十分だった。真弘は心の中で両手を挙げる。
(降参だ。もう、自分の気持ちに嘘はつけない)
「ありがとう。お礼に今度、蘭泉プリンスホテルのアフタヌーンティーに行かないか。……二人で」
彼女の顔が桃色に染まり、表情全体で喜びを表す。その日こそ、この気持ちを伝えよう。隠し、押し殺そうとしても抑えきれなかった、君への想いを――
本編へつづく