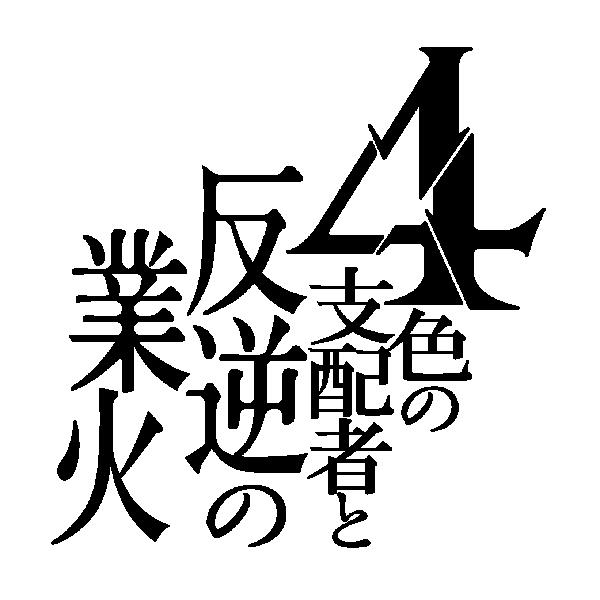
深い、腹の底に響くようなため息がこぼれる。
そのまま柔らかな椅子に体を預け、ぼんやりと部屋の中へ視線を巡らせる。
この王城の中心にあるホールは、宗教美術館を模して僕がつくらせた。
床は、あえて絨毯を敷いていない。
細やかな模様を施した美しい大理石を覆うことになるからだ。
深い青のアーチを描く柱の上には、ステンドグラスの高窓。
大輪の青薔薇が咲いているように国中の大工を集めて趣向を凝らした。
そして、何よりも壮麗なのは、聖人の彫刻のかわりに配置した、何十体もの美しいマネキンだろう。
その心臓たちは未だどくどくと鼓動を刻み続けている。
しかし、涙を流す人形の瞳にもはや光が宿ることはない。
そう……僕は、人間を生きたままにマネキンにすることができるのだ。
「いつ見ても、いい眺めだね」
広く寒々とした室内に僕の声が響いた。
つやつやと輝く美しい肢体。
物言わぬ生者。
ただそこに在るだけの存在。
それはなんて素晴らしいことなのだろう。
「ここにまたひとつ、素敵なコレクションが追加されるのだと思うと、とても楽しみで仕方がないよ」
そう言いながら、ふと、先ほどまでの笑みが引いていくのを感じ、頬に手を当てた。
我ながら生気が無い皮膚で、いっそ氷のようにひんやりしている。
目を閉じると、今日出会った少女の存在がチカチカとまぶたの裏を刺激するのを感じた。
彼女は今頃何をしているだろう。
冷たい牢獄で後悔しているだろうか。僕と出会ったことを。
毎月一度、城から街へおり、僕は美しい少女をひとり選ぶ。
選んだ少女はもちろん、こうしてマネキンにして飾るのだが……今回の少女は少し勝手が違っていた。
だって、無色の民の生き残りだ。
馬車から降りたとき、そしてその瞳を間近で見つめた瞬間、すぐに気づいた。
純粋に復讐に燃える炎をあの澄み切った透明な瞳に宿していたのだから。
ならば彼女は、我ら有色の国を脅かす無色の民に違いないだろうと。
それでも……いや、だからこそ余計に欲したのだ。
じっと、黙ったまま僕を見つめるその瞳の強さ、美しさ。
青の国の者ではない、その肌の不思議な透明感。
触れればすり抜けてしまいそうな危うさと儚さを持ち、それなのに、その体にたぎる熱はこの国を焦がしてしまいそうなほどに激しい。
今までにそんな瞳を持つ人間が目の前に現れたことがあっただろうか。
「本当に……不思議なことだ……」
十年前、皆殺しにしたはずの無色の民が生き残っていた。
しかもあんなに美しく脆そうな少女が。
心臓が苦しくなる。
あの少女のことを考えていると、心臓が締めつけられるように苦しくなる。
毒を持っている、毒を持っているのだ。彼女は毒を持っている。
彼女の体に宿っているのは、心ではなく、毒。
彼女の仲間を殺した僕を絡め取る、毒……。
分かっているよ、分かっているんだ。
分かっていて、僕は君を招き入れた。
だって、面白いだろう?
君がどんな風に僕を殺すのか、見ものじゃないか。
そして彼女が復讐に失敗した時、僕は彼女を最高の作品に仕上げてやることができる。
僕の前に打ちひしがれ、絶望の淵で涙を流す彼女を、僕は美しい美しいただ唯一のマネキンにすることができるんだ。
復讐心を持つマネキンなんて、これまでにいなかった。
きっとこれからも現れない。
『あなた様に、こうして触れる日を夢見ておりました』
椅子から立ち上がると囁きが聞こえた。
彼女の声だった。
『あなた様に、こうして触れる日を夢見ておりました』
振り返ると、再度彼女の声が聞こえる。
僕はそれを再び繰り返しながら、ゆっくりと口を開いた。
「そうだね、君はそう言って僕に触れたよね」
『幸せでした』
「本当に僕に触れたかったの? 君は、無色の民の生き残りなのに? 僕は君の仲間を殺した憎き青の王なのに?」
するとそれきり、彼女の囁きは聞こえなくなる。
思い出すのは、今日、彼女が僕に触れたこと。
まだ幼さの残る顔で、小さな唇で、必死に僕に奉仕をした。
あの熱い口内。
いやらしい光景を思い出しているとめまいがしてくる。
下腹部に、熱い疼きが生まれ始める。
きつく目を閉じ、椅子に背を押しつけるようにもたれかかった。
あの時の衝動はなんだろうか……。
性欲だけではなかった。
彼女が僕に触れた瞬間の衝撃、そして僕が彼女に触れた時の、あの激しい衝動。
激しい……深い……。
「喜び……?」
いや、そんなばかげた話があるわけがない。
僕はこのままで十二分に満足しているのだ。
わがままなど言わない、愛してくれなど言わない、ただ美しいだけのマネキンに囲まれているじゃないか。
恐ろしい生き物だ、無色の民は。
元々あの種族には、人外な能力が備わっていると聞く。
僕はそれに、絡め取られそうになったのだ。
そうに、違いない……。
「馬鹿げているよ。さっさと僕を殺しにかかればいいのに、君は一体、なにがしたいんだ……」
ゆっくりと少女が頭をもたげる。
心に描く彼女の強い眼差しが僕を射貫く。
どうか、どうかそんな目で僕を見ないでくれ。
見るならばもっと憎しみの視線で、怨みをこめた視線で、僕を見てくれ。
訳の分からない熱を燃やした透明なその瞳は……僕を壊してしまいそうになるんだ。
かつん、と靴音を立て足を踏み出す。
整然と並んだマネキンを横目に、ホールの出口へ向かった。
途中、自室へ寄り毛布を一枚手に持つ。
そのまま、あの少女のいる部屋へと足を向ける。
マネキンになる少女には、食事も衣服も与えない。
ただひたすらに体を清め、少しでも美しいマネキンになれるようにするのだ。
「…………」
少女のいる牢獄の重い扉を開くと、床に横たわり丸くなっている少女が目に入った。
ぴくりとも動かない。
まさか死んではいまい、と真っ直ぐに少女に近づく。
月明かりと小さなランプひとつしか彼女を照らし出すもののない室内で、少女の体はぼんやりと青白く薄闇の中に浮かび上がっていた。
思わず息を飲む。
本当に死んでいるのか……?
と、心の声が唇からこぼれかけた矢先、少女がぴくりと動いた。
「っ……」
「……王……様……?」
眠っていたのか、とろりとしたまぶたを押し開きながら、少女が僕を見上げる。
その刹那、どくんと激しく体中の血管が脈打った。
ああ、どうして。
どうして僕は、この少女をさらったのだ。
どうして、どうして……!
今すぐにでも、彼女をマネキンにすべきだ。
そう、今すぐにでも。
明日の朝には必ず、彼女をマネキンにして……マネキンにして……もう僕のことを、そんな目で見たりなどしないように、僕の心臓を掻き乱したりなどしないように。
すぐにでもマネキンにしなければ。
そうしなければ駄目だ。
そうしなければ……。
ほら、言うのだ!!
「毛布だ……」
裸の彼女の上に、投げ捨てるようにして毛布を落とす。
彼女は不思議そうに毛布を見つめ、それからすぐにくるまると、僕を再度見上げた。
「ありがとうございます」
「……礼などはいらないよ。どうせ君と会話をするのも、あと少しだけだ。君はただのマネキンになるのだからね」
言いながら声が震えるような気がして、早口で言い切る。
彼女の声はいつも、少しだけかすれて、か細い。
まるで無理矢理に言葉を押し出しているかのように。
きっと、無口なせいだ。
ふだん言葉を紡がないから、そんな風に、かき消されてしまいそうなほどに弱々しくなるのだ。
明日。
明日、マネキンにしなければ。
明日だ。
そう言うだけだ。それなのに――
「今日おこなった体の清めは、明日からも毎日おこなう。以上だ」
唇は勝手にそんな台詞を紡ぎ、体はそのまま背を向けてしまう。
足は身勝手に前へ進み、手は当たり前のように格子を掴む。
……なぜだろう……。
僕は彼女の声を、まだ聞いていたい…………。
青の真意2話に続く