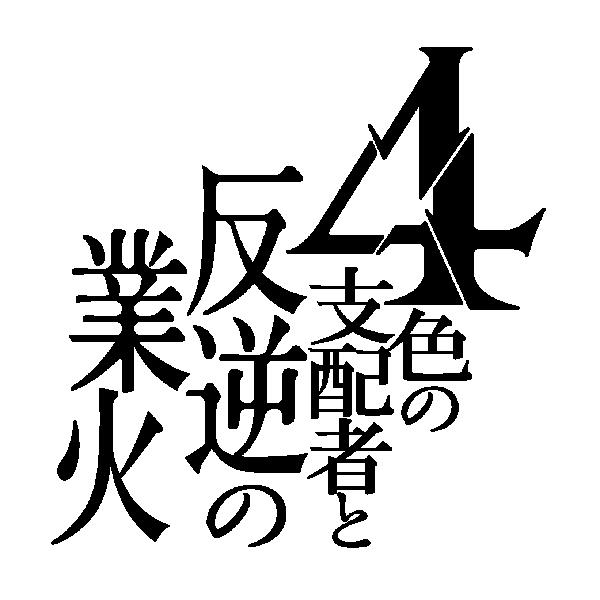
その日の夜は、雲の陰りひとつない美しい夜だった。
幾千の星に包まれた月はひっそりと微笑んでいたけれど、女の囚われた牢に続く通路には窓ひとつない。
暗がりを照らす燭台の光がおぼろげな足元を照らし、大理石を蹴る足音だけが高い天井に響く。
やがて女の囚われている牢の鉄格子が見えてきた。
錠前を開ける指先がいやに重く感じられる。
あの女に自らの犯した過ちを、今日こそは必ず認めさせる……。
そうでなければ、僕の信じてきたこの世界が、足元から崩れてしまう。
生々しい欲の匂いを放つ愛などに、人々が救えるものか……。
あの悪魔の甘言に耳を寄せてはだめだ。
そのための準備に、僕は一度深く呼吸をすると、ゆっくりと扉を開いた。
しかし、壊れた弦楽器のような音を響かせ扉が開くと同時に、僕は硬く戒めた心を一瞬にして手放してしまいそうになった。
「神よ……どうかあの方の心に安寧を……癒しを……」
女の姿に、そして言葉に、思わず息を呑む。
小部屋の入り口に灯された炎が、緩やかにしなる女の背骨を照らす。
膝をつき、一心に祈りを捧げる姿はまるで、幼き日に見た宗教画の聖母のようで心臓が震えた。
どうして神様は、このような存在を僕の元に遣わしになったのですか。
人々を卑しい肉欲に落とす穢れた者が、なぜ僕の目にはこうも美しく見えるのですか。
僕は目の前の光景を受け入れることができずに、その場から後じさった。
「……法王様?」
振り向いた女の長いまつげが揺れて、瞳が開かれる。
炎の小さな揺らめきは、彼女の瞳を蠱惑的に輝かせる。
「罪を認めない限り、決して神は、キミの願いを聞き届けないよ……」
女の穏やかな微笑みを跳ねのけて、僕の口は刺々しい言葉を放つ。
そうしなければ、一度揺らぎかけた決意が取り戻せそうになくて、僕はそれがとても恐ろしかった。
だって、まるで……。
僕の心が、この女の醜く穢れた愛によって作り替えられているようで……。
でも、そんなことは認められるはずがない。
「法王様……」
女の瞳に悲しみが映り、吐き出した言葉の苦味が胸に広がる。
女は唇を噛み、うなだれる。
艶やかな髪が肩からこぼれ、白すぎるうなじが露わになった。
礼拝施設で思い出しかけた行為が、脳裏に鮮やかに像を成す。
僕はくらくらしてきた頭を押さえ、心に何度も言い聞かせる。
心を揺り動かされるな。
その儚くも妖しい姿に絡め取られるな。
内心の動揺を気取られないよう、抑揚を捨てた声を絞り出す。
「……悪魔が……神になにを祈るというの……」
「法王様の幸せを……この先の無事を。どうか、あなたの心に安らぎが訪れますようにと」
女の答えに、彼女に見えないよう背に回して、手を握りしめた。
どうしてそんな言葉を口にできるのかと、胸に広がる苦みがいっそう強くなる。
「昨夜……僕の体に汚らわしい行為を働いた身でかい」
「お嫌でしたか……?」
「……なんてしらじらしいことを言うの……」
すると亡霊じみた細い姿が立ち上がり、僕に手を伸ばした。
また一歩後じさりそうになった足が、しかしその場を離れない。
まるで女の美しさに魅入られたように。
「法王様……そんなことをおっしゃらないでください」
「キミこそ、そんな顔をしてもだめだ、僕は騙されない。キミは穢れているんだ、罪人なんだ……人々に淫らな行為を働く悪魔……なのに……」
そんなキミを、僕は美しく感じてしまうなんて。
(お前はそれでも神の子なのか)
神の叱咤の声が聞こえる。
胸に下げた十字を、無意識に掴もうとした手に、悪魔の指先が触れる。
細い指先は、柔らかで弾力があり、呼気にも似た湿りを持っている。
「っ、だめだよ、いけない。僕に触れてはいけない」
「なぜですか、私の指は法王様に触れてはならないほど、穢れていますか?」
「そうだ、だってキミは悪魔だ」
「それでは私の穢れた指が触れるだけで、法王様の神々しさに曇りが掛かると言うのですか。神の加護の光とは、そんなに簡単に失ってしまう程度のものなのですか?」
「それは……。でも、僕に触れているキミの指先は……昨日、僕の……」
牢の空気がねっとりと重い。熱が思考を妨げる。
呼吸を何度繰り返しても、淫らな昨晩の行為のひとつひとつが鮮明に像を結び、僕の内側からただの人に過ぎない部分を炙り出す。
「あなたを愛しているからです」
「嘘だ、キミの愛は間違っているのだから、その言葉は真実じゃない」
「では人の愛は罪ですか。愛する者に触れ、情を交えたいと願うことは穢れたことですか」
白い指先が十字を握りしめた僕の手の上を滑る。
指先は器用にボタンを外すと素肌にそっと触れた。
「ぁ……っ」
触れるな……!
そう、叫びたかった……。
汚らわしい指を払いのけたかった……。
なのに女の浮かべる微笑みが、僕の唇から言葉を奪ってゆく。
心さえも優しく取り込もうと指先は更に滑り、シルク地のシャツ越しに僕の心臓を撫でる。
「法王様……今夜も私に会いに来てくださった……」
「だめだ……こんなこと……許されない……神がお怒りになる」
このまま掴まれて持っていかれたら……。
この心が、神を愛する気持ちごと、絡め取られてしまったら。
神はもう、二度と僕を許されない……。
「だめだ、だめ……だから」
「法王様……」
なのに、許されないと知りながら、僕はこの悪魔を振り払えない。
だって、このぬくもりを受け取ることが許されないのなら、人はなにに縋ればいいの。
人々に、神の奇跡の代行者として許しを与える僕は、誰に許されればいいの。
この体はもう、この悪魔の手によって穢れてしまったというのに。
もうただ潔白なだけの身で、以前のように神を信じることは、できなくなってしまったのに。
「触れないで……お願いだから……僕をこれ以上苦しめないで……」
触れたい。触れられたい。でもこれ以上深い場所は、探られたくない。
肉体に相反する精神が、蜘蛛の巣にかかった羽虫のように、僕の内側で醜く抵抗する。
このままでは、神に罰せられる前に、僕の心が壊れてしまう。
僕が僕でいられなくなってしまう。
「法王様……どうか、私にあなたを癒すことをお許しください」
「だからだめだと……っ、いいかげんその手を離さないと僕はキミに罰を与えなければいけなくなる!」
「それであなたの心が救われるなら……」
「……嫌だ……」
「法王様、どうぞ……この卑しい体に罰をお与えになってください、それであなたの心が救われるのなら……」
女が僕に近づく。
僕の言葉をそのまま呑み込んでしまおうと、ついにその唇が僕のそれに重なりそうになる。
その時、大聖堂の鐘が鳴り響いた。
厳かな鐘の音に時が止まる。
僕はその中で目を見開いていた。
女の唇はどこまでも柔らかく優しかった。
神の御心よりもずっとあたたかく、確かな存在を持って、その細腕は僕の心を包んだ。
僕はその生きたぬくもりを、やはりその晩も振り払うことができなかった。
* * *
重苦しい音を響かせて鉄格子が閉まった。
僕は振り返ることもなく、乱れた胸元を正し、女のいる地下牢をあとにした。
もう認めるしかないのかもしれない。
僕はあの女に愛を感じてしまっている。
神の与えてくださる愛とは別の、もっと生々しく実態のある強い欲を。
そして神に逆らうような行為に自ら溺れようとしている。
「ああ……神様、僕はどうすれば……」
祈りとも懺悔ともとれる言葉に答えは出ないままなのだった。
END