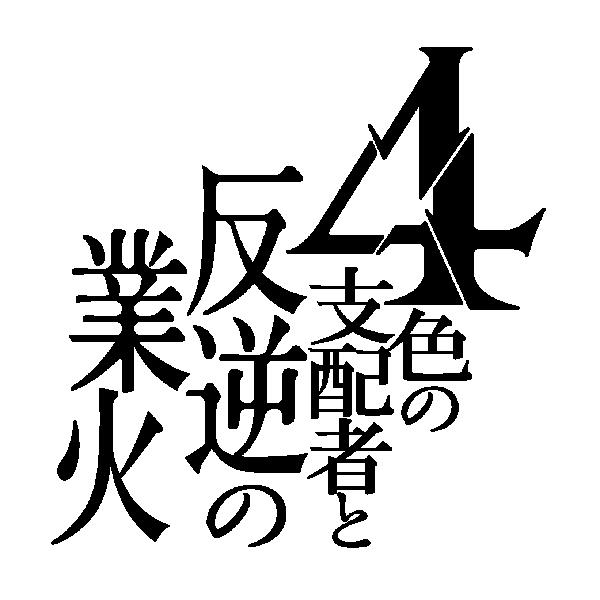
「法王様、どうか……」
人々が詰めかけた教会の祭壇で老婆がうやうやしく目をつむる。
「そなたに神の祝福を……」
しわの刻まれた額に手のひらをかざし、決まりきった麗句を口にする。
すると老婆は神の深い慈悲に涙し、骨と皮ばかりとなった両手を擦り合わせて、幾度となく感謝の言葉を述べた。
安息日には僕はこうして各地の礼拝施設を巡る。
無辜の人々に、神の教えを説くために。
神の最も純然たる愛を伝えるために……。
ステンドグラスから差し込む厳かな光の帯。
列を作り、祈りを捧げるこの国の民は、僕の姿に神の代弁者を見るのだろう。僕を見る皆の目には、一様に深い畏怖と敬意が映る。
聖なるもの、穢れなきもの。それがこの国の王。白の国の皇帝にして法王。
だけれども。
たった今祝福を授けた右手が震える。
この手はもう、汚れてしまった。
あの女のせいで、穢れを知ってしまった。
こんな汚らわしい手をして……。
それでも僕にはまだ、人々へ神の愛を説く資格があるというの……?
「法王様、わたくしにもどうか浄化の光を」
次に頭を垂れて僕の足元に膝を着いたのは、あの女とそう年の変わらない、髪の長い女だった。
だけど慎ましやかに祈りを捧げる姿は、地下牢で処刑を待つあの女とはまったく違う。
(法王様……)
耳に残る、風が揺れるような声。
あの可憐な囁きは本当に悪魔の声なのか……。
だとしたら僕は……。
(法王様、あなたを愛しているのです)
どうしてあの悪魔は……。
神の教えのみを信じてきた僕の心に柔らかな爪を立てた。
甘美な声で、淫靡な舌先で、生暖かい心臓を包むように、僕の内側に入り込もうとする。
(法王様……)
鮮明に記憶に残る声は、まるで耳元に直接声を吹き込まれた気がするほどに、僕の心に染み込んでいる。
そして、昨夜の行為を鮮やかに脳裏へ映し出す。
(もっと……声を聞かせてください。法王様)
(こうすると……ね、もっと気持ちがよいのでしょう?)
柔らかに、花を愛でるように、しっとりと……。
昨夜、青白く透き通った指先が僕の芯に触れた。
果実めいた赤い舌がのぞく口元で僕の唇を誘って。
肌と肌は重なり合い、皮膚の薄い粘膜を緩く指はなぞった。
あの悪魔の美しい指先は、僕の体に触れるだけで、僕の胸を開き、まるで血を分け合うように、僕の心をあたたかく満たした。
(私は愛しているのです)
(たとえ私の愛が、法王様の説く愛とは遠く離れ、穢れていようとも)
月明かりだけが差し込む夜に、声は甘く僕を誘った。
体の内側が熱く、なにかに炙られる。
脳が甘さに浸されそうになり、聞こえるはずのない声が耳元に響く。
(法王様……)
「……っ」
ああ、最悪だ。こんなのは。
神の御前を前にして僕はなんてふしだらなことを思い描いている。
こんなのはすべてあの悪魔の見せた幻だ!
「法王、様?」
「……っ」
いぶかしげな声に頬を冷水に叩かれて、顔を上げる。
行き先に迷う子羊の目がこちらを見上げていた。
分厚い法衣に包まれた背を汗が伝う。
戻された現実は、どこまでも神の息吹に満ち溢れた神聖なる場所だった。
窓から入る五色の光が、僕の心を責める。
お前はこれでも神の子なのか。
光は、神がそう僕を叱咤するようで、僕は緩く目を閉じる。
しっかりしなければいけないのに。
神の教えを。そう、今は民に神の教えを説かなければならないのに。
望まれるまま、説法を。神の慈愛を。
こんなにも僕は穢れてしまったというのに。
淫らな追想を振り払うために、手にしていた錫杖で強く床を突く。
僕は、法王だ。
神に選ばれたこの国の法王だ。
あのような悪魔に、心を惹かれているわけがない。
あれが、あの悪魔のやり方だ。
屈してはいけない。
あの女がどれだけ優しい言葉を投げかけようと。
神に教えられることのなかった歓びを僕に与えようと。
意志を強く持ち、落ち着き払った笑みを口元に浮かべる。
「……この免罪符をお持ちなさい。あなたの罪が浄化されんことを」
「あぁ……! ありがとうございます、法王様!」
人々の唱える祈りの句に混じり、感嘆の声が上がる。
女は免罪符を胸の前で握りしめ、僕を神そのものと崇めてその場から去って行く。
「やはり、さすが法王様……」
「神の申し子……」
「この国の王……」
「法王様……法王様……」
僕を中心にして、人々の賛辞の声がさざ波となって教会に広がる。
(法王様……)
教会を揺らす声に混じり、またあの罪人の女の声が聞こえた。
嘘だ。
今、聞こえるはずがない。
「…………っ」
振り切ろうとも、あの甘い声が追いすがってくる。
僕のただ美しいだけだった愛に、欲に満ちた指先で触れたあの女の声が消えない。
すべてあの女がいけない……!
あの女のせいで、僕の心は穢れてしまった!
このままでは僕をかたどっていた虚構が脆く剥がれ落ちてしまう。
本当は神の申し子でもなんでもない、ただの人にすぎない姿が民の前に晒されてしまう。
あの女をどうにかしなければ。
あの女は罪人だ。
人の心の隙間に入り込む悪魔だ。
礼拝の時間が終わり、僕は国の中央たる大聖堂に戻るため馬車に乗り込んだ。
ひとり、ひっそりと神に祈りを捧げる。
「神よ、どうか罪深いこの身をお許しください……」
小さき頃から教えられるままに何度となく口にした祈りを唱える。
心に満ちる神の愛を感じながら、やはり祈り合わせた手のひらを見て思う。
まだ、僕は戻れるのだろうか。
それともこの身はやはり穢れてしまったのでか。
あの女の口にする愛で。
淫らな愛で……!
女の姿を思い浮かべること自体が、神への裏切りにも感じ、込み上げてくる苦みを飲み込む。
「今夜こそ、あの女に罪を悔い改めさせなければ……」
固く胸に決意する。
馬車の窓から外を見る。
大聖堂の立つ丘に続く道は赤い夕陽に照らされて、さながらあの女のはらわたに誘われているようだった。