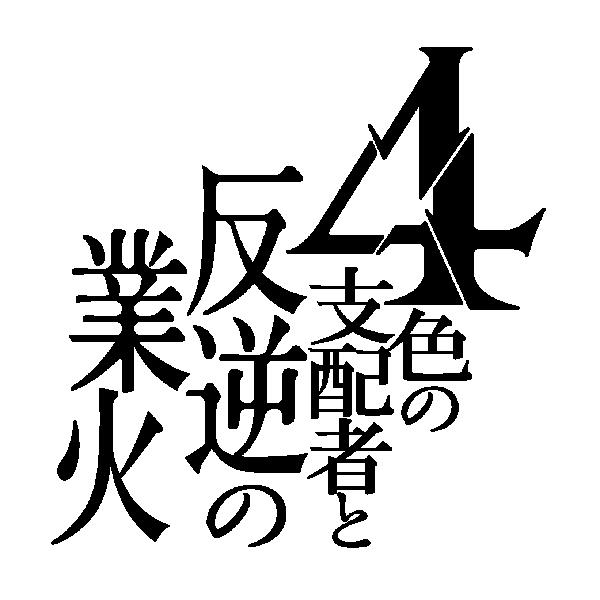
金細工と石造りのオーナメントで装飾された大浴場には、柔らかな湯気が立ち込めていた。
日に焼けた肌に、湯をすくった女の手のひらがやんわりと触れる。
恐れを抱いているのか、指先の動きはずっとぎこちない。
まさか、この女も湯浴みの手伝いを申し付けられるとは思っていなかったのだろう。
おずおずとした指先の動きに合わせ、水面に映った布ひとつ纏わない美しい裸体が、ゆっくりと揺れる。
「なんだ、そんなにこの隻腕が気になるか?」
視線を感じそう問えば、女は頬を赤らめて目を伏せた。
既に何度か辱めてやったというのに、いじらしい真似をする。
しかし返答がないのが気に食わない。少しいじめてやりたくなり、女のあごを掴み上げた。
「貴様、さっきはなぜ逃げた。そんなにこの俺が怖いか? 憎い復讐相手だろう。そんなことでどうやって俺の命を奪うつもりだ?」
「……っ、おやめください!」
引き寄せたあごを強引にこちらへ振り向かせると、女は体を縮こまらせて、さえずった。
非力さゆえ、そして自分の立場ゆえに、抵抗したくとも満足にできないのだ。
この女の生殺与奪の権利は俺が握っている。
俺の気が変わり女の内情を人前で明らかにすれば、すぐさま捕らえられ、二度と日の目を見ることは叶わない。
いや、そんな面倒なことをするまでもなく、今この手に少し力を入れ、首を捻ってやるだけで、この女は容易く命を散らすだろう。今まで俺が屠ってきた多くの命と同じように。
しかし俺の腕の中で体を捻る様があまりに弱々しくて、声を出して笑ってしまう。
「相変わらずだな。そんな抵抗では、俺は誘われているのかと勘違いしてしまうぞ?」
「ご冗談を。王様が無体を働くのがいけないのではないですか」
「ほう……無体とは?」
形の良い柔らかな乳房を、濡れた手で掴む。
強めに揉みしだけば、指が柔らかな肉に食い込み、押し潰れた白桃は、手によく馴染む。
柔らかく、包み込むように吸い付く肌は、温かい。
「あ、ぁっ……おやめ……くだ、さい……」
「こうして……頬を上気させて、目を伏せては……。俺が強引に貴様の体を割り開こうとした時と、何ひとつ変わらないではないか」
なまめかしい体をねじる度に、音を立てて、水面から湯が飛び散る。
鷲掴みにしたバストの先端で赤く色づく果実を指の谷間で挟んでやる。女は一瞬、引っ詰めた声を響かせ、しなやかな裸体をビクつかせた。
またのどが鳴った……。
今日はどのように辱めてやろうか。
息も絶え絶えになるほど、その体に刻み込んでやろうか、この俺を。
首筋に舌を這わせ、花の香りにも似た女の匂いを胸に吸い込む。
これは男を知る、甘い女の匂いだ。
俺の腕の中ではなすべくもないが、王城にたったひとりで忍び込む気概のある女だ。まさかこれまで生娘であったなどとは思えまい。
しかし、この女が他の男に組み敷かれるのを、想像したくはなかった。
独占欲だろうか?
そんな感情をこの俺が持つとは。つまらない。
それとも無色の民を蹂躙していると興奮でもしているのか。
これまでも勝利の美酒に酔いしれ、快楽のままに女を抱くことはあった。
しかし目の前の柔肌に高揚することはあれど、この女に手を出す時のように、胸の奥に得体のしれない存在を感じることはなかった。
この女は簡単に手折られる弱々しい姿を見せながら、いつも心に別の感情を忍ばせている。
様々なものをくゆらせ、一言では言い表せない光を目に湛える。
同胞を根絶やしにされた悲しみ、復讐の業火、復讐に対しての迷いと恐れ。
奪われた者の持つすべてと、それだけではない何かがそこにある。
女の目尻に涙が浮かぶ。
涙に濡れた瞳は、やはり俺をじっと見つめ、逸らされることがない。
そして苦しげに顔を歪める時に、垣間見せるのはいつも……。
「王様……王様……」
「だからどうして貴様は……そうさみしげな目で俺を見るのだ。今なら俺は丸腰だ、仇討ちの絶好の機会だとは思わんか? 俺を殺したいほど憎んでいるんだろう。なのになぜそうしない」
「王様……」
女が首を振る。
返事を待つのにじれて、乳房から指を滑らせ、腹を辿り、薄い繁みを掻き分けて、指を秘部へと突き立てた。
「……っ!」
「それとも復讐が怖くなったか? 仲間を殺された恨みは、まだぬらぬらとお前の心を炎で炙っているんだろう? その上こうして……辱められ……。なのになぜ、そんなさみしそうな目で俺を見る」
何色にも染まらず、光を反射するだけの瞳は、怯えながらも俺の知らない色を映し、もの悲しく輝いていた。
『復讐』という、それこそ赤の民の象徴でもある炎のような感情を宿していながら、どこまでも美しく。
しかしその瞳を見続けていると、自分すら気づかなかったものを女の瞳を通して気づかされるようで、心の奥底に仕舞い込んだ何かが疼き始める。
失くした腕が痛むのか。
戦場で負った傷が痛むのか。
この熱に似たものはなんだ……。
女の目がもう一粒、涙を零す。
涙に映るのは、赤の王。この俺の顔。
その欲と権力に塗れた俺の顔は、誰も信じようともせず、愛せもしない、悪鬼の形相をしている。
涙は無言で、そう語りかけていた。
* * *
女を下がらせた浴場で、水滴の伝う天井を呆然と仰ぐ。
妬まれ、殺し、多くに恨まれ、王城の一番奥まった場所であろうと、いつ寝首をかかれるかと、心安らぐこともない。
そんな自分に果たして、愛など抱くことができようか……。
「何を期待しておるのだ、俺は……」
自らへの戒めかもしれない。
自国と民を守る為とはいえ、お前はこのように憎悪に瞳をぎらつかせる者をたくさん生み出してきたのだと。
この先安寧など訪れるはずないのだと。
だから、あのような女を手元で飼う、戯れなど思い付いたのか……。
「馬鹿な。感傷に過ぎん」
あの女はやはり生かしてはおけない。
殺そう。
このようなじれったい気持ちは……女と共に殺してしまおう。
そう決意し、失った腕の付け根に爪を立てる。
胸の内に生まれつつある急いた感情を、今はまだくゆらせながら……。
END