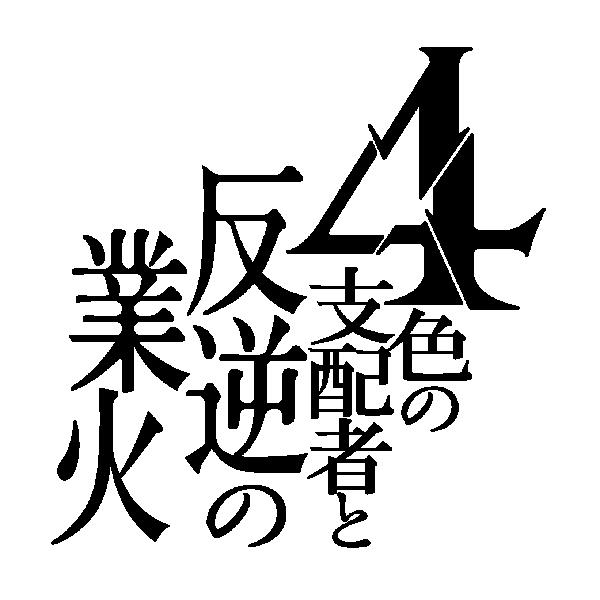
曇天の闇に沈む路地裏を疾走する。
土砂降りの雨が石畳を濡らすなか、足音を頼りに角を曲がれば、震える手でナイフを握る男がこちらを睨んだ。切っ先からは血が滴っている。
「く、来るな……、俺がなにをしたっていうんだ……っ」
「うるさい、喚くな。生きるに足らない……罪人、風情がっ!」
男の落ちくぼんだ眼光が生臭い光を放つ。
刃先が赤くぬめるのは、今しがた罪のない女を切り裂いたからだ。
その一部始終を暗がりから見ていたのは私だ。
彼が罪を犯すのを止めもせず見ていたのだ。
目の前の男をとにかく今は殺したい。
体の内側を喰らいつくすようなおぞましい衝動に抗えない。
殺戮の乾きの奴隷と化した肉体は、ただひたすらに血を求めていた。
殺せ。殺せ。殺せ。殺せ。殺せ。
脳内で繰り返される声は既に声ではなく、耐え難い不協和音が鳴り響いていた。
痛み、疼き、狂気、高揚、そして恐れ。
それらすべてを振り切るようにして、手にした魔剣を振り下ろした。
断末魔と共に赤黒い血が灰色の壁に飛び散った。
返り血を浴びた自身を抱きしめるようにし、赤く染まる床に膝をつく。
体は震えていたが、しかし胸に広がったのは後悔でも恐怖でもなく安堵だった。
「っ……これで……、少しは、治まる……」
『彼女』を殺さずに済む。
そう思うと、なにがおかしいのか、口の端から気味の悪い笑いが漏れた。
深く息を吐き出す。
辺りには死臭が漂っているが、それが今ほど屠った男のものなのか、自分の体から漂っているのか、判断がつかない。
分かることはただひとつ。
数日前から、おのれの胸の器を満たしていく、不確かなものの存在。
見えもしないなにかが確かにそこにはあり、違和感が膨れ上がる。
「これも……あの女のせいなのか……?」
日に一度、女の元に向かい、彼女の差し出す盃に毎夜決められた量だけ注ぐ。
盃が水で満たされた時こそ、この体に巣くう病が癒される。
それが女と私の間に交わされた約束だった。
「しかし、この……胸の奥にあるものはなんなのだ……」
最初は取るに足らなかった違和感が、女の元に通い続けるたびに強くなっていた。
「私は、どうしてしまったんだ……! 忌々しい病だけでも手に負えないというのに……」
緩慢な動作で立ち上がり、雨に濡れた仮面をつけ直す。
そして、剣を鞘に収めようと柄に手をかけた時。
「ぐ……っ」
心臓を鷲掴みにされるような痛みが走り、胸を押さえた。
まだだ……まだ足りぬ……!
殺せ。血を、肉を……命を差し出せ!
悪魔が直接頭に響く。
「っ……、まだ……殺し足らないのか、この体はっ!」
胸に注がれた違和感の正体を知りたくとも、体を蝕む病が許さない。
もう、解放されたい。この長く続く苦しみから。
自分はいつまで出口のない苦痛に悩まされればいいのか。
こうして血の衝動に駆られるたびに、人を殺してまわればいいのか。
人影すら見えない路地裏を振り返る。
雨の匂いに混じり、どこか遠くから生きた人の匂いがする。
外套を翻し、私は地面を蹴った。
きっと今の自分は、醜い血に飢えた獣の顔をしているだろう。
残された理性の片隅でそう思うも、数秒後には人の心を手放し、私は路地を駆ける影となった。
* * *
衝動が静まって城へ戻る頃には、雨は止み、空が明るみ始めていた。
私は返り血を大雑把に洗い流し、隠し扉を潜り、女の元へ向かった。
約束の水を注ぎに行かねばならない。
女の持つ盃が満たされるその日まで。
一日、一日、必ず満たしに行かねばならない。
「女、今日の分だ」
「ありがとうございます」
恭しく差し出された盃にわずかばかりの水を差す。
水音を響かせながら、少しずつ、少しずつ、盃が水で満たされていく。
「っ……」
その時だった。
私の外套から一筋の血が腕を伝い水差しを伝い、盃に落ちたのは。
盃の中程まできた水面が、新たに差した水で揺れる。
そこに垂れた血が蛇のようにとぐろを巻き、美しい水を不吉に色づけた。
不吉だ。
それを見ると同時に胸の内側がぐらりと揺れた。
女が盃を取り上げ、次に私を見上げ、頭を垂れた。
まがまがしい血が誰のものか。怪我はしていないのか。
普通ならそんなことを尋ねてくるだろう。
なのにこの女はそんなことなどどうでもいいのか、この神聖めいた儀式を汚したことに、咎めるまなざし一つしないのだった。
「これで何日目になる?」
「七日目になります」
「あと、三日か……」
女は、部屋の片隅に設けられた石造りの台座に盃を据えた。
通風のために括り付けられた隙間から、雲間を抜けた光が差し込む。
夜明け前の微かなものとはいえ、忌むべき光を浴びる気にはなれない。目元に手を掲げ、光を遮る。
誰もが寝静まるこの国の夜明けは静かなものだ。
青白い光。少し水気を帯びた空気。
冷たい床に座り込んだまま、盃を見つめる女も口を開かない。
程なくして私は小部屋から出たが、物言わぬ女ともうふたつみっつ言葉を交わせば、もしかしてあの違和感の正体が分かるのではないかと思い、再度扉をくぐった。
「どうかなさったのですか?」
「少し、君に聞きたいことがある」
「なにを……?」
よく磨かれた水晶のような女の瞳が、微かに細められた。
得体の知れない異国の女……。
だが、この国の国王がみな同じ病で死にゆくことを知っていた。
そして私をも蝕むその病を治せると言う。
しかし……。
「君は囚われの身だ。この部屋に君がいることは、私以外誰も知らない。私がこうして部屋へ訪れなければ、君はやがてやせ細り、餓死してしまう。それは……分かっているな?」
「はい」
「だが私は、この身を脅かす病を治すために、こうして毎晩君の元に水を注ぎにやってくる」
台座に据えられた盃に視線をやる。
水面は一条の光を反射し、薄暗い部屋の中でそこだけ浮き上がって見えた。
神聖な泉のように。あるいはなにか大切なものの象徴のように。
「なぜ、君は私を病から救おうと思った? こうして命を握られているとはいえ、見ず知らずの男をなぜ……。哀れだとでも思ったか?」
女は口を開かない。
沈黙が再び流れるが、私は構わず言葉を続けた。
「私は……君の盃に水を注ぎに来るたびに、思っていることがある。君がどうして病を治すなどと言い、こうして一見意味もないことを私にさせるのか」
「……なにかお気づきですか?」
ふと、一瞬だけ美しい顔に陰りが見えた。女の瞳と視線があう。
「君はもしや……、私のことを最初から知っていたんじゃないのか?」