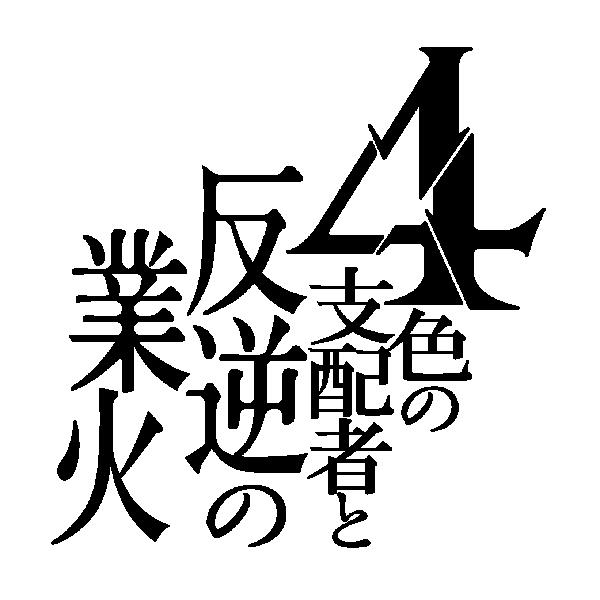
「王、ご無事ですか!」
あぶみから降りて、鷹が捕らえたウサギに剣を突き立てると、後を馬で追ってきた従者に声をかけられた。見れば顔が青い。なんのことかと思ったが、頬に飛んだ返り血を見て、俺が怪我をしたのかと思ったらしい。
「構うな、ただの返り血だ」
「な……そうでしたか。これは失礼いたしました。鷹を追いかけた姿が急に見えなくなりましたので、落馬でもなさったのかと」
「貴様、この俺を隻腕だからと侮るか? そのようなヘマをするか」
「めっ、滅相もございません!」
従者の男が慌てて頭を下げる。不興を買ったことを咎められるのを恐れているのだ。
頬を手の甲で拭うと、確かに血の匂いが鼻をついた。
公務もない風の穏やかな日のこと。
この日は、朝より数名の従者を連れて鷹狩りに出かけたのだ。
ただ青い空の下を馬で駆け、気晴らしをしたかっただけなのだが、王たる者が単身で平原を駆るわけにもいくまい。
「さすが王! これは大物ですな」
獲物を仕留めたと聞いて、その場に他の従者たちが駆け寄ってくる。
「戦の申し子と言われるだけあって、剣捌きも実に見事! 急所を一突きで仕留めておられる」
「叶うことなら我らも戦場でそのお姿を拝見したいものです」
「ははは! まったくもってその通り、王がいればこの赤の国は安泰ですな」
「ふん……口ばかり忙しい奴らだ……」
保身しか考えぬ小うるさい文官ごときが……。自らは決して戦場になど赴かぬくせによく言うわ。
心の中でそう罵倒し、方々からかけられる声には答えず、剣を骸から引き抜く。
気に食わない。
顔色をうかがうばかりの声や目が。
俺は知っているのだ。
人の心にすくう欺瞞を。恐怖を。卑劣さを。
誰よりも、知っているのだ……。
媚びへつらった表情を見せるこやつらも……。
顔に張り付けた薄っぺらい皮をひと剥きすれば、内側に見えるのはみな同じ。
どうしょうもなく狡猾で、薄汚れた醜い顔よ。
しかし、それを責めることなど俺にはできない。
この国を、同族殺しの血で血を争う戦いでもって治めた俺には……。
「王、それでは次なる獲物はどちらですかな?」
「それよりも、そろそろ小休止を挟んでは?」
「もうそんな時刻になるのか」
従者に言われ天を仰ぎみると、太陽が中天に差し掛かろうとしていた。
雲ひとつない空の下、乾燥した空気が頬を掠める……。
この土地は元々、内乱で最後まで抵抗した長兄が治めていた土地だった。今でこそ国土のすべてが我が領土となったが、視線の先に見える丘の下を掘り起こせば、数年前の戦で命を落とした者たちが今も眠っている。
自らを死に至らしめたこの俺に、禍々しい怨念を抱いたまま。
この手は、血に濡れている。
様々な不運と巡り合わせがあったにせよ、俺は今さら許されることのない恨み妬みを買い過ぎた。
その上、戦いの果てに手に入れたのが、顔色ばかりをうかがう下らん家臣共と、恨みを買う者にいつ寝首をかかれるかと、おちおち寝てもいられぬ夜とは……。
俺もつくづく救われん男だ。
「王様、王様……!」
いつの間にか追憶に沈んでいた意識が、遠方から聞こえてきた女の声で、現実に呼び戻された。家臣に連れられて、バスケットを手にした女がこちらにやってくる。
「あの女……、飯炊き女がこのような場所まで何用だ?」
頭をすっぽりと覆ったフードの下で、無色の瞳が瞬くのが見えた。
意識せずのどの奥がくつりと鳴った。
返り血を浴びた頬をもう一度拭うと、丘を吹き抜ける風が妙に熱く感じた。
同胞を皆殺しにされ、復讐を胸に俺の命を狙い、この城に入り込んだ女。
今は亡き無色の民の生き残り……。
なぜ、そのような内情を知りながら、女を城に置いておくのかと問われれば、ただの戯れだとしか答えようがない。
細い女の肢体は抱き心地こそいまいちだが、見目麗しく白く透き通るようなきめの細かい肌は、指を這わすとシルクのような滑らかさがある。その肌の感触が気にいった。
「おい、誰だ。この場にたかが飯炊き女を呼んだのは。貴様か? それともそこのお前か」
「いえいえ、まさか」
「城で何かあったのではないでしょうか。誰か知らぬか?」
従者たちに視線を配るが、否定か疑問ばかりを口にする。
「ならばその女が自ら俺の顔を見に来たのか。どうなんだ、女?」
「はい、私は……」
女は俺の元に来るとフードを上げた。
女の瞳に陽の光が差し込み、本来色を持たないはずの瞳が微かな色を持つ。
女が心に抱く復讐心かとも思ったが、煮え滾るような思いに入り混じり、迷いが見え映る。
無色の民は何色にも染まると言うが……。
本来ないはずの色に、なぜか俺は惹きつけられた。
「昼食の支度がととのいましたので呼びに参りました。狩りを楽しんでいるところ、お邪魔でしたでしょうか?」
「昼食だと? ならば出かける前に言伝でもしておけ」
「申し訳ございません。調理場には、王様がお出かけになった後、連絡が入りましたので……」
「貴様の言い分などどうでもいい、こちらに来い」
申し訳なさそうに頭を下げる女に手を伸ばす。
及び腰になった女の視線が揺れた。
「何をしている、城へ戻れと言ったのは貴様ではないか。俺の馬の後ろに乗れ」
「王様……!? そのようなこと恐れ多くてとても!」
瞳が困惑に彷徨うのを見て、強引に女の細腕に手を取ろうとした
しかし、触れるかどうかというところで、細い指先は俺の手をすり抜けて行く。
「も、申し訳ありませんっ。私はただの給仕係ですので、どうか先にお戻りくださいませ」
恐れを抱き体を小さくする女の瞳に、先ほどまでの光は見えない。
霞を掴んだかのような頼りない感覚に舌打ちする。
「相変わらず気の利かん女だ……まあいい。貴様ら行くぞ」
「はっ、今すぐに!」
城に戻るため、家臣と共に馬を走らせるが、手綱を引く手に自然と力が入った。
思い通りにいかない女の態度に、胸の奥が収まりの悪いもので満たされる。
あれは無色の民の生き残りとは言え、なんの力も持たないただの女だ。
復讐という短剣を胸に忍ばせていようと、実際に刃を振り下ろすこともできない、ひ弱な女だ。
ならばなぜ、俺はあの女を手元に置き続けているのか……。
「この俺が、こうもままならん気持ちを抱くとは……」
風を受けながら馬を走らせ呟いた声は、誰の耳にも入らぬまま草原へと置き去りにされた。