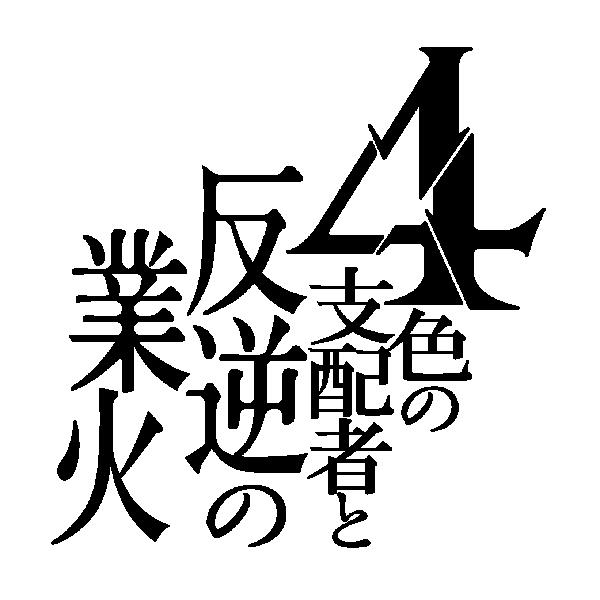
「君はもしや……、私のことを最初から知っていたんじゃないのか?」
私の問いからしばらくして、女の顔に落胆とも安堵とも取れない不思議な表情が浮かんだ。
「違うのか?」
「……この黒の国の王であるあなたを知らない者などいないのでは?」
女の今までと変わらない返事に、知らず口元が歪んだ。
こいつは答える気などまるでないのだ。
「腑に落ちん答えだ……」
ゆっくりとため息をつき、女からやや離れた床に腰を下ろす。
石畳の冷たさが身に染みて、このような所にずっと閉じ込めていては、女の身には酷だったのではないかと、今更になって気掛かりに思う。
「寒くはないのか?」
足を引きずり、女の元に近づくと、白い頬に指を伸ばした。
しかし冷たく見えた陶磁器のような肌は、ほのかにあたたかく、むしろ雨に濡れ続けた自分の指先が、女の体温によってじわりと感覚を取り戻す。
指先から女の穏やかな熱が流れ込む。
温められた血潮が、指先から私の心臓へと巡る。
違和感ばかりの胸の器に、ぬくもりが注がれるように感じた私は、つい指先を跳ねさせ、女から遠ざけた。
「王……?」
「……なんでもない。君は見た目よりずっとあたたかいのだな」
「王が冷たいのです」
彼女は私の手に自らのそれを重ね、頬ずりした。
まるで私の手が愛しいそれであるかのように。
「冷たいのは体だけでない。心も、と言いたいんだろう?」
ずくりと胸が振動する。
内側に飼った野蛮な獣が起き出しそうになったのを感じ、目を固く閉じる。
頼む。今この場でだけは起きないでくれ。
あれほど屠っただろう。血を捧げただろう。
私は……私は……この女を殺したくない……!
「っ……ぐ……っ」
「王!? 大丈夫なのですか!」
瞬時に顔を青くした女が、苦しみに喘ぐ私の元へ身を寄せた。
肉体の内側を這いずる疼きに耐え切れず、伸ばされた白い指先を強く握る。
すると、少しだけ苦しみが和らぐように感じた。
「しばらく……このままで、いて……くれ」
絞り出すように伝えると、女は私の背をゆるく包むようにして答えた。
どれだけの間、女の指に縋るような真似を続けていたのだろう。
長い長い時が、音もなく過ぎていった。
女は何も言わず、私の指を握り返し、もう片方の手で私の背を優しく撫でもした。
やはり指先はあたたかく、私はそれだけでも随分と救われた。
「王様……お寂しいのですね」
「……知らん、そんなわけがない。君には関係がない」
人を殺して安堵したとは伝えたくなかった。
伝えることに意味はない。いや、あるのだろうか。病の症状を伝えればあるいは……と、思考の糸が乱雑に絡まり始める。
詳細に思い出してみればどうだろう。
だが、返り血に濡れた瞬間を思い出して、また衝動が抑えられなくなったら、その時こそ私はこの女を殺してしまうかもしれない。
「王様……」
「少し、黙っていて欲しい。……君の言葉を信じるのも悪くないと、思っただけだ。時を待てば……あの盃に水が満ちれば、私はこの病の苦しみから救われるんだろう……?」
女に初めて会った時は、確証もない言葉など信じる気になれなかった。
万にひとつにでも可能性があるならばと、考えただけだ。
だが病のせいとは言え、これまで殺戮を繰り返し、人ならざる闇に落ちた私に、救いなど許されるのだろうか。
「私が、必ずあなたを救います、その先になにがあろうと必ず」
「救いか……」
誓いじみた言葉を耳にし、顔を動かし女の様子をうかがった。
瞳に映る色は嘘偽りない真実だ。
ようやく楽になってきた体を捻り、女の膝に身を預けた。やや眉が寄せられた美しい顔越しに何もない天井を見る。
「ひとつ君に私の過去を聞かせてやる」
「王様が……」
いつも静かで落ち着いた様子の女が、めずらしく驚いたようで、水晶の瞳がかすかに見開かれる。
私は女の瞳から視線を移し、盃の方をぼんやりと見ながら口を開いた。
「もう何年も前になる。私は、ある一族を皆殺しにしたのだ。この病のせいもあるが……あれは、私自身が犯そうとして犯した罪だ」
「……っ」
黒い痣を作った私の体を撫でていた女の手が止まる。場の空気が変わるのがわかった。だが女が手を止めたのはほんの一瞬で、私が目を閉じると、女は私の手に自分のすべらかな手を重ねた。微かに細い指先が震えている。
私はしばらく口を噤み、女の様子がそれ以上変わらないことを確認し、続ける。
「今更その罪を償えるとは思わない。しかしその時、どうしてもひとりだけ殺せなかった女がいたのだ」
「……なぜ……ですか?」
「分からん。昔のことのうえ、あの時は辺りの血の匂いが酷く、人らしい判断などできなかった。だが……」
「教えてください。なぜなのか!」
女の言葉が普段より幾分鋭い響きを持つ。
感情を失した女だと思っていたが、案外押し殺していただけなのかもしれない。
閉じていた瞳を開くと、澄んだ無色の瞳が厳しい熱に潤んでいた。
「おそらく……復讐のためだ」
「復讐? でも、王は……」
あの無色の民の王宮で、逃げ惑う人々をひとりひとり切り捨てていった時、最後に残った女は、顔をこわばらせながらも、炎に照らされた瞳にだけは、淡い光を湛えていた……。
そして今、まぶたを開けば、まさに目の前で、夜明け前の青い光に照らされた、あの時と同じ静かな光と視線が合う。
「ひとつでも命を救ったと思えば、少しは胸が晴れる」
「それだけですか」
「いやもうひとつ。後に私を殺しに来る者が現れると思い生きれば」
「……」
「きっとあの日の光景を何度夢に見てもそれをよすがに生きていけるだろう」
「後悔されているのですね」
「いや……あれは必然だったのだ。後悔などはしない」
「では、やすやすと殺されてやりますか」
「それも無理だろうな」
珍しく女が声をたてて笑った。
「君の元に水を注ぎに来るたびに、あの時と同じ説明がつかないもので胸が詰まる。病の疼きとは別の……もっと甘く、心苦しいものが私の中に生まれるんだ」
盃を水で満たすたびに感じるもの。
胸の器に、知らない海が広がる感覚……。
「私の思い違いならそれでいい……だが……君はもしや」
「王様、これ以上はどうか口にしないでください」
寂しそうに瞳が伏せられたかと思うと、女の指先に瞑目を促された。
仮面を隔てているはずなのに、指で覆い隠された目が熱い。
胸の奥も窮屈で、熱い……。
このままこの女の元に通い続けては、いつか心の器から溢れた水で私は窒息するのではないだろうか。
だとしても、病に心ごと喰われていくよりはきっとマシだろう。
「もう間もなく朝がやってきます。だからどうか今はこのまま眠ってください。約束の時が訪れた時にはすべてお話しますから」
小さく囁かれた声と暗くなった視界に、徐々に睡魔に誘われる。
女の言う通り、もう眠りにつく頃合いなのだ。
眠りに落ちる瞬間だけは、病のもたらす疼きも忘れられる。
「おやすみなさい……王様、ゆっくりと……」
既に、女の言葉は耳に届いてはいなかった。
しばしの休息に意識を手放す。
胸の器を満たしていく水の名を知らぬまま……。
END