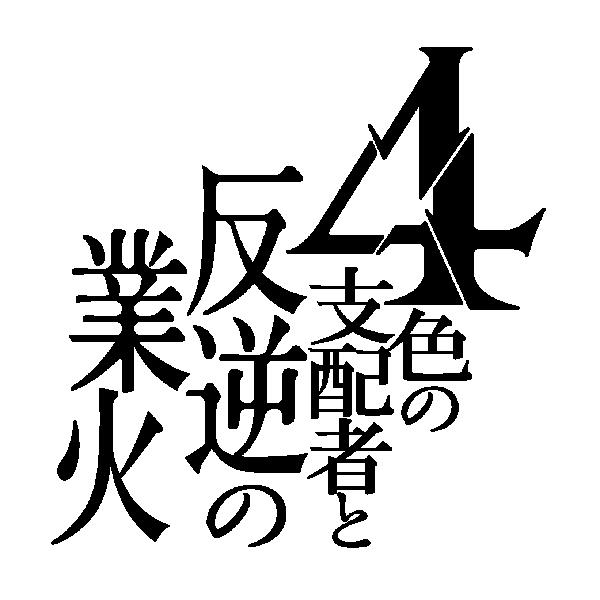
無色の民の生き残りである彼女を、この城へ引き入れてから何日が過ぎたのだろうか。
何度日は昇り落ちたのか、もう数えてもいない。
いつもの僕ならば、既に完璧なマネキンを作り終え満たされた気持ちになりながら、完成したばかりの物言わぬ少女を眺めている頃だろう。
こんなのはおかしい。
彼女を飾るべきスペースはぽっかりと空いたまま、僕は今日もその空間を眺めているだけ。
「今日も、彼女の体を清めなければ」
いつものごとく、城の中心にあるホールの中、僕はひとりつぶやく。
重い腰を上げ、なにかに操られるように彼女の元へ向かうのだ。
いつもなら、飾ったマネキンの顔や体をひとつひとつ確認する。
いつもなら、このホールの美しい高窓のステンドグラスをゆったりと見つめる。
いつもなら、一刻も早く新しいマネキンが欲しくて心が震える。
いつもなら、いつもなら、いつもなら……。
いつもならそうであるすべてが、今回はなにもかも違う。
僕はホールを出た。
やはりいつもとは違う、熱くはやる気持ちをくすぶらせながら。
* * *
彼女を閉じ込めている牢獄へ足を踏み入れる。
敏感に僕の足音を察知するようになった少女は、すぐに僕の前まで走ってきてこうべを垂れた。
するりと彼女の肩から、薄っぺらい毛布が滑り落ち、青白い裸体があらわになる。
小さく、つばを飲み込んだ。
「お待ちしておりました」
か細く消え入りそうな声で少女は言う。
僕はそんな彼女を見下ろしている。
痩せた体はどことなく痛々しく、マネキンにするには食事を抜きすぎた、とはたと気づく。
ゆっくりと下げていた頭を上げ、僕を見上げた彼女の瞳は、出会った瞬間と変わらず、いやそれ以上に深く澄み切り、僕を射貫いた。
どくん、と心臓が騒ぐ。
どっくん、と体中の血管が暴れる。
あっという間に、下腹部が重く熱い熱を沸かせ、恐ろしい欲情のかたまりとなって僕の体をかき乱し始めた。
「寒くはないかい」
「……いいえ、寒くなどございません」
「そうか、君の手はいつもひんやりと冷たいからね」
「申し訳ありません、どうかお許しを……」
言いながら、彼女が僕の熱に触れる。
ズボンの前をかき分け、それを手に取る。
ああ、と僕は心の中で熱い吐息をこぼす。
そのひんやりとした手が、僕は好きなのだ。
まるでマネキンのように、熱を持たぬ冷たいもの。
けれども確かに生きている人間の手。
彼女は、僕の前で動き、しゃべり、そして惑わす美しく邪悪な生き物。
「ん……っ」
彼女が、その小さな口に僕のものを頬張る。
熱はいっそう強く僕を打ちつけ、劣情をあおり、どこかへ突き落とそうとうねり始める。
やめてくれ、やめてくれ、と彼女の髪をつかむ。
けれども僕の指は、無情にも彼女の髪の間を滑り抜けてしまうのだ。
だから再度つかむ。
きつくきつく。
憎しみをこめるようにきつく。
いつも通りの僕を奪う憎き彼女の髪を、強くきつく、乱暴に。
つかむ。
「ん……んんっ……」
彼女が苦しげに顔を歪める。
僕はその妖艶にも映る表情にあおられるように、今度は両手でその滑らかな髪をつかんでしまう。
駆り立てられるままに、欲情のままに。
苦しい。
熱のかたまりに殺されてしまいそうだ。
彼女の唾液が、彼女の熱い口内が、そして彼女の冷たい手のひらが、僕の心臓を止めてしまいそうなほどに、強い脈動を刻ませる。
「……もうやめろ……やめてくれ……」
ねめつき絡みつく彼女の唾液や舌に、僕はかすれた声を発する。
もう幾度、こんなことを繰り返したか。
もうどれだけ、僕はやめてくれと思い、そうしてまた求めたか。
「ん……ん……」
彼女はやめない。
僕が彼女の口内へ精を解き放つまで、決してやめないのだ。
ああ……苦しい……。
きっと僕だって苦悶の表情をこの顔に刻みながら、彼女を見下ろしている。
薄く血管を浮き立たせた震えるそのまぶたを。
涙を滲ませる大きな瞳を縁取る、濃く長いまつげを。
小ぶりな曲線を描く、鼻筋を。
淫靡に濡れた、小さな唇を。
細いあごのラインから伸びる首筋を、浮き上がった鎖骨を。
美しく主張する、その乳房を、引き締まった華奢な腰を。
僕は、僕は見下ろしている。
毎日毎日、目の前の美しく儚い少女を……見下ろしている。
「やめろ……」
「……んっ……」
「やめろと言っている……」
「っ……」
「やめないか……っ!!」
「きゃっ……」
思わず感情のままに彼女を突き飛ばすと、なんの抵抗もなくあっさりと、小さな体は弾き飛ばされた。
冷たい床に倒れ込み、それから悲しげな顔で僕を見上げる。
そんな顔で見ないでくれ。
どうかそんな顔で僕を見ないで。
一歩、彼女ににじり寄る。
「……申し訳ございません……」
肩を震わせ、少女は謝罪を口にする。
「なにを謝っているの。なんのために」
問うと、彼女は答えない。
僕は彼女をぶってやろうと手を振り上げ、すると彼女は反射的にぎゅっと目を閉じ、僕はその顔が美しかったので制止した。
そしてあろうことか、気がつけば彼女の体をきつく抱きしめていたのだ。
冷たい、冷たい体だった。
ひんやりと、この国の氷のように冷たく、それなのにその体の芯からは確かな律動が聞こえる。
脈打っている。
生きている。
心臓が、動いている。
薄い皮膚の内側から、確かな温かさがやってくる。
じんわりじんわりと、僕の体に伝わってくる。
包み込んだこの腕に、密着させたこの体に、温かさが伝わってくる。
それは、汚らわしい熱情とは別のもの。
熱く冷たく温かく、僕の心臓を包み込んでしまう、不思議なもの……。
「これが心だなどと……信じない……っ」
知っている、分かっている。
彼女は僕への復讐心をその胸にずうっとたぎらせていること。
心などは存在しないこと。
ましてや愛などは存在しないこと。
分かっているのに……ないはずの、心が痛む……。
ああ、違う違う、これは心臓が痛いだけだと思いながら、そうしていると、すうっと彼女が僕の背に手を回し包み込んだので、どうしようもなく苦しくなった。
彼女の手は、腕は、とても柔らかく優しいのに、僕はまるで拘束されたかのように動けなくなって悲しくなって、さっさと、一刻も早くこの少女をマネキンにしなければ、とまた思った。
何度も何度も自身に言い聞かせ続けたその覚悟を、また胸の中でつぶやく。
マネキンに、しなければ。
心などあるはずもない。
ましてや愛など、あるはずもない。
それなのになぜ……!
僕はこんなにも、彼女を欲しているの……。
「抱いて、くださらないんですか……?」
無口な彼女が、懇願するように僕の耳へ言葉を吹き込む。
僕はきつくきつく彼女を抱きしめ、その首筋に顔を埋めた。
堪えきれなかった涙が一粒、床に落下し、それが悔しくて悔しくて、彼女の背に爪を立てる。
そうだ、もうマネキンにはできないよう、彼女の体に傷をつけてしまえばいいのだ。
そんな思いを胸に抱きながら、僕は彼女をまた突き飛ばすようにして部屋から飛び出した。
この手にかき抱いた温もりが今すぐに消えるよう、念じながら――。
END